2022年10月7日、1985年に浜松市で生まれた竹山友陽さんに初めて会った。場所は浜松市内の「みかわや」でした。あれから2.5年、思うところあって、「竹山友陽入門」を始めます。2年間かける予定ですが、どこへ到達するのか、目的は何かなどは定めていません。第一回の話合いを2月18日におこない、そこで竹山さんの半生を確認しました。このweb頁はそのときの印象を元に、上空や過去に遡り眺め、まとめおきます。
(はじめに)
「地形と水と人の暮らしは密接不可分なもの」、と考えるのは建築設計をなりわいとしてきた佐藤の性癖かもしれない。
理由を記せば、24才のとき小さなシュークリームを生産するための、大きな洋菓子工場を千葉県のピーナツ畑の真ん中に設計し建造した。上水も無い!下水もない!見渡す果てまでピーナツ畑だ。春一番が吹くとローム層の細かい土が舞い上がり、人も車も一寸先も見えず前にも後ろにも移動できなくなる、ピーナツの台地は春先、台地の地獄を見せる。工場はこの細かな埃もブロックしないと売り菓子はつくれない。そういう地域に300mの井戸を掘り、台地に降り注いだ300年前の水をくみ上げる。同時に工場からでる排水を処理する活性汚泥方式の処理施設を造り綺麗な水に戻すことで、ようやく小川に流す許可がでる。計画、許可申請そして工事まで設計と監理に含まれていたので、てんてこ舞いで対応し地形と水の循環を身体に叩き込んで覚えた。
独立系建築士になった30代前半には山奥の旅館の事業計画と設計をおこなった。水道は山奥には来ていない。規模を大きくし成立させる事業計画に先立ち、奥羽の山から湧き出る規模に適した水源を探し当てないと、計画はなりたたない。そのために目の前にある川をたどり沢をえんえんと登り進む。突然山の中腹から、伏流水が湧き出す。この川はこんなところから始まるのか!水が地球を循環する本来の姿に立ち会うと不思議な高揚感が生まれる。それは自身の身体の水と湧き出したばかりの水が共振し合い感動がうまれるからだろう。
水を探し当てたら次は下水処理施設を造る計画を練る、場所や処理方式を決める。
辻琢磨さん、竹山友陽さんと偶然出会い浜松市の地形や高架になった鉄道網なども体験させてもらっている。辻さんには天竜川の川面と二俣川の氾濫した場所を案内してもらい豪雨のあとをながめた。二人はサッカー友なのでサッカーの歴史とその現状も「竹山友陽入門」を通じ深堀し源流を遡上してみたい。
はじめに浜松市街の地形、次にサッカーの歴史を概観していこう。
友陽さんが生まれるまえの浜松市と地形
浜松市街は天竜の流れが作った扇状地にある。福島市も扇状地で盆地だが、太平洋には面していないので、空気がよどみ夏は高温、冬は底冷えしやすい。浜松市を流れる馬込川と天竜川は一体で、流れくだり扇状地を形成し広大な遠州灘に面している。だから市街地をのぞけば全体は海風、山風がたえず吹きかうので空気が爽やかで暮らしやすそうだ。
大きな中州に浜松の町ができたとも言えるし、洪水のたびに流れは激変したのだろうから、治水が完成していない時期に人々は浜松城のある少し高台に居を構え暮らしただろう。三方原台地は酸性土壌だそうだ。古人の骨は溶解し見つからないが、もし人骨が残っていたなら遺跡は三方原台地の東面を北上するようにあったと想いたい。また、浜松駅そばには佐鳴湖、さらに西に進むと浜名湖があるので、狩猟採取民には暮らしやすい領域だったろう。
三方原台地には明治維新によって仕事が消滅した士族たちが入植し、お茶を栽培しようとしたが良い結果をなせず雲散霧消してしまったそうだ。士族たちが消えてから約50年、日本は敗戦し中国大陸などから多数の引揚者が帰国した。行き場のない引揚者の一部が三方原台地にも多数入植することとなった。
敗戦が金原善明の描いていた三方原台地の開拓を促進することになったとも言える。金原は、天竜川に(秋葉)ダムを造り水路を敷設し、台地全体を水田、耕作に適した水のある農業生産の高い場所に替える夢を描いていた。金原の夢は国家プロジェクトにかわり1990年頃完成したそうだ。軍の爆弾投下地帯は農地に代わり浜松市の農業生産が一気に拡大した。(参照動画:やらまいか精神と水資源+竹山友陽さんの実家そばにある金原善明記念館)
1985年、浜松駅そばで生まれた竹山友陽さんは、お母さんの実家がある浜北区をたびたび訪問していたと語る。最近のことだが、亡くなったおじさんの供養のためおこなわれた「遠州大念仏」を辻さんと共に観たそうだ。友陽さんは無意識にせよ三方原台地の突端を東西に行き来し北にある山裾も訪問している。浜松市の地形を十字に体験し、現在も地形との交流は保たれ、浜松市は平成の大合併によって北奥の山々まで浜松市と称されるようになり、市役所の職員だって、竹山さん自身もその地の名を知らないと語っているほど広い。天竜川が八ヶ岳や諏訪湖から流れ来ていると知らない市民もいるかもしれないほど、各地の多様な水を集めて今日も、やすまず流れている。
(未来はない、今を生きるを推す!)
1981年、友陽さんが生まれる5年前のこと。現在、小説家になっている町田康さんは『メシ食うな!』と題するファンク・ロックを歌い、日本経済バブル前夜を見据え大阪をベースに、小説や落語から引いた言葉をもちい、純化しないカッコよさをスカシ目指し無茶する、一瞬を楽しむミュージシャンだった。大阪の暮らしと無関係なのに外国人を猿真似し続ける日本のミュージシャンに怒りを向け『メシ食うな!』と歌ったのだろう。瞬時に消える素人の馬鹿力が生みだした音楽ともいえる。で、町田さんが飯を喰わなかったわけでもなく、一般の社会人にむかって「メシ食うな」とアジったわけではないだろうが、45年後の現在、歌の存在さえ知らない人は多いかもしれない。
サッカー選手が日々ボールに触れ練習し続けるように、ミュージシャンも日々歌いつづける。同様に人は日々飯をつくり食べる、この繰り返しが人に生を与える。食材を手に入れ調理し盛り付けて食べる。食べ終わったら後片付けをし食器を整え明日へつなぐ。単純極まるルーティンワークの偉大さを忘れ、ショートカットし前のめりに活動すると、思わぬ害を自身の身体や暮らしを支え育む基礎環境にもまき散らす。
川面から水をくみ上げ料理し体内に注ぎ込む、身体を通過すると「汚水」と呼ばれ外部化する。身体を離れたとたん以前自身の内部だったそれらも、知らない無縁の事物になる。水は身体の外部からやってきて身体を通過すると汚水となり、汚水処理施設で処理することで川の流れに戻すことができる。
浜松市に暮らす人々が上水位置を眺め、自身の汚水処理され水がどこから天竜川に戻るか眺めて、しみじみ知る人が何人いるか知らない。ましてや上水と下水がどのように区分けし管理しているのか、それを積極的に学んでいる市民は極すくないだろう。
山紫水明の国・日本では上下水を長らく意識せず暮らすことができた。自身の身体が大自然と一体になることを自覚せず暮らすことが可能だった。敗戦後、工業化による商品の生産が過度に進み、海外へ輸出しお金を稼ぐことが目的化した敗戦後の高度成長期。そこへ至ると、自身の細胞と天竜の流れが共振し合っているのを感じる人はいなくなってしまい、河川は汚れ放題だったろう。
天竜川の流れは諏訪湖から幾多の障害をこえ、うねうねと流れくだり遠州灘に到達する。太陽があたえた力と地形の落差が生み出す単調な繰り返しの中に天竜川の幸いと害は同置している。害と受け止めるか幸いと受け止めるかは人の欲望が起因していて、多様なそれを生み出し続ける。
「竹山友陽入門」を始めることは、天竜川の流れを観て想像しては記録することに似ている。到達知、あるいは到達地点は必要としていないし、どのような流れを描くのか分からない。集う人々の呼吸、長い語り合いの中からたくさんの源流を探し当てては循環を企てながら、その過程の喜びを記録していきたい。


三方原台地用水経路図
やらまいか精神と水資源─三方原用水のあらまし (2015年頃か)
■サッカーの歴史
工場労働者じゃなかった竹山友陽さんとサッカー関係の前に
福島県立図書館にいきサッカーに関する書籍を調べてみた。幅90センチほどの開架の書棚には400冊はないだろうか、棚2段に並んでいるだけで、他は書庫に眠っている。備え付けのPCで検索し4冊ほど当たりをつけ借りた。県立図書館にはサッカーに関する書籍がどれほどあるのか、まだ分かっていない。こつこつ調べていくことにする。
その日は7冊借りてきたので、書影と刊行日を右欄に貼っておく。それらに目を通して知ったことは、サッカーの歴史・源流は詳しくわかっていないこと。FIFAがパリにできた経過をみて、「160年の歴史しかない」と知った。明治維新の3年前だから2025年から160年前だからついこないだのこととも言える。
(FIFA以前のこと)
サッカーの源流は日本の伝統芸「蹴鞠」だろう、だから中国から輸入されたものだと思い込んでいた。ギリシャではエピスキロス→ローマ帝国でハルパストゥムと呼ばれていた競技だそうだが、それらの資料が佐藤には無いので詳細は不明だ。
1992年3月メキシコに点在する遺跡を訪ね歩いた。モンテ・アルバンに行くと最初に球戯場に出くわすのだが、サッカー場にしては狭すぎる。山頂でインディオたちがどのような球技をおこなっていたのか、今でも分からない。先導者の渡辺豊和さんによると、幅5m、長さ25mぐらいの細長い競技スペースで、どのような球戯をしたのかちょっと想像できないが、メキシコ、インデオの『古事記』にあたる『ポポル・ブフ』を読むと、彼らは有史以来、この球戯を神事としておこなっていたらしい・・・。

球戯場 1992年 佐藤撮影
(FIFA前夜 スポーツもルールを作る人が世界を支配する)
FIFAは英国に4つの協会を認めざるをえなかったようだ。イングランド、スコットランド、ウェールズ、アイルランドの4協会。一国一協会が原則、英国は破られているのでサッカーの歴史を川の流れを遡上するように見ていこう。
英国では12世紀から民族フットボールによって町と町、村と村を敵に見立てて、ルールなく、手足もつかいながら暴力ありで一つのゴール点を目指し競いあっていた。詳しくは分からないのだが現在も行われているようだ。
1575年 ケンブリッジ大学で学生と村人の試合が行われ大乱闘が勃発したことで、乱闘防止のためケンブリッジ大学構内のみで試合をすることに決める。まだサッカーとラグビーが分かれていず、試合中に乱闘も発生していた。同時に、スペインやポルトガルに続き大航海で富を集めまくる世だ。宗教改革を契機に大英帝国が世界各地に植民地経営をおこなう。英国内では産業革命によって少数の経営者と大多数の工場労働者に分かれることになる。各企業がチームスポーツを奨励することで、奴隷ではない労働者たちの内部には労働時間と余暇時間という考え方が生まれる。男たちはフットボールに熱中し憂さ晴らしをし合ったのだろうか・・・。一方、鉄道網もでき労働者の移動手段が拡大すると、対外試合も設定し実施しやすくなったようだ。
1857年ケンブリッジ大でルール作りが行われ、シェフィールドという名のサッカークラブもできた。1863年ロンドンには13の組織ができ、大組織独自のルール作りでもめたそうだ。ケンブリッチは足だけ使う、手も使うラグビーに分かれた。
くりかえす、19世紀前半は工場労働者が多数登場したことで専属選手と観客に分離する。鉄道網も整備され、ルール作成のもめ事から統合はなせず、フットボールはラグビーとサッカーに分かれる。以前は農業や狩猟、楽しみはダンスで、そこで体を動かし連帯や共感を醸成していたのだろうが、19世紀後半からは世界中でスポーツ熱がたかまったそうで、当時の場に立ってスポーツのルール作り争いを観察し記録したい、との欲望が沸くものだ。
20世紀にはいると国際試合が始まり、サッカーは国際化し1904年FIFAがフランスのパリに設立される(ヨーロッパ7ヶ国を統合組織)オリンピックゲームの中にサッカーもあり、プロ、アマ混在の時間が長らく続く。1928年 FIFA ワールドカップ開催宣言。第一回開催はウルグアイで、審判暗殺と買収対策を施したうえ、それぞれのボールを使いわける始末になったそうだ。
(日本、プロスポーツの誕生)
日本は1868年、明治維新を契機に近代化が急速になされるなか、世界の帝国主義にも参加。80年ほどで敗戦という国民国家の破綻を経るが、その間は東アジアンの国々を植民地経営に乗りだす黒歴史を持つ。武術以外の球戯スポーツは正岡子規も愛好した野球がすこし行われる程度だったようだ。
1945年の敗戦後、正力松太郎は世界屈指の新聞(読売)社をつくりだし、日テレ、ゴルフ場、遊園地経営、読売巨人軍を宣伝源と手法とし盤石な経営基盤をつくりだす。政界に進出し総理の椅子を狙った。(参照:『巨怪伝』)同時に原発をイギリスから輸入し原発の父とも呼ばれている。彼はスポーツ界にも影響を与える地位に立ち、頂点は天皇・皇后を後楽園球場に座らせ観戦させたことだ。一方プロレスをTV街頭放映し、プロ野球も普及させ新聞の販促に手抜きなく、庶民の余暇時間とお茶の間を占拠し、生を消費させつづけ「平和ボケ」と呼ばれる国民を誕生させた。
それ以前のサッカーはオリンピックの一つの種目であり、企業対企業の合戦で宣伝を兼ねたチームが主だった。その中からオリンピック出場選手が選ばれるという時間が続いていた。日本のプロ・サッカーは1993年、Jリーグ誕生まで待たねばならない。それ以前のサッカーのスターと言えば1944年生まれの釜本邦茂で、かれは参議院議員も一期つとめた。日本では2025年現在もオリンピックで名を馳せ、参議院議員になる男女はあとを絶たない。もしかするとプロサッカー選手が参議院議員に当選する日もあるかもしれない。
(サッカーのスポーツビジネスあれこれ)
半生記、『クリスティアーノ・ロナウド』に目を通したが、プロサッカー選手の害や闇について多数思うところがあった。今後、竹山さんと語り合い記録することし、ここでは触れない。彼は、移籍金額 2272億円、2024年の年収400億円ほどでアスリート一番の収入をえているそうだ。
それ以前の高額選手は1982年のマラドーナ20億円でFCバルセロナへ。2001年のジダン80億円でレアル・マドリードへ。 2017年ネーマールを280億円でパリ・サンジェルマンへ。2018年エムバベを260億円パリ・サンジェルマン獲得。
2011年、カタールがサンジェルマンを買収したことにより中東の石油資本が一気に流れ込みサッカー界のバブル現象はとどまることをしらず。今後サウジアラビアでワールドカップが開催されるという。原油による資本の一極集中は今世紀にはいると、投資先がなくなり株取引から一部、サッカービジネスへ移行しているようだ。
( 1978年から商業化)
オイル・マネーは偏った地域の地底から湧き出るお金なので、富が偏り、温暖化も加速させるので、油を使わない、代替えを生み出すなどの覚悟は求められるはずだ。
協会はチケット販売、放映権の売買、グッツ販売、CMなどで利益を生み出す。そうしてサッカークラブへの投資。選手の金銭的価値激増は民族フットボールの世からみれば、資本主義の悪弊にまみれ、スポーツ本来の道から遠く離れてしまって、お金の多小をもって起動させてしまう。同時に世界を舞台にした政治的な出来事になったことを確認することが肝心のようだ。
金銭がサッカー渦にエネルギーを与え続ける、そこへ時間をもて余す大衆が一気になだれ込。さらにサッカーにエネルギーをあたえる状態が続いているようだ。サッカーは地方色と神事を遠くはなれ、単純化されたことで、お金まみれを呼び込むことになった。そのことで何が起きるのか、選手たちとファンが語り合い悪所を見出す、後に浄化システムを手に入れる。そこからようやく次の新しいサッカーが生まれる。今後、そのことは両者の欠せない行為だと気づく人が多くなることが第一歩だろうか。
美しかった天竜川の流れを人が汚水に変えた世もあったが、事の重大さと害に気づき浄化システムを構築し、対策をたてたことで(ダムはたくさんあるが)、天竜川の流れを多少回復させたように、サッカーの流れもやがて回復が求められるだろう。
サッカー選手自身に倫理を求める気はないが、組織を運営する者には求めざるを得ない世がみえている。資本主義下のプロスポーツにはお金が集中しやすく、組織も選手もバランスを失しやすい。「竹山友陽入門」を通じて語り合うなかで、FIFAの一極管理の害悪や選手の金まみれ問題も話題にあがるだろう。そして、そのプロサッカー界も浄化しようとする一手法の萌芽を見つけ確認することができるかもしれない。
第一回竹山友陽入門の記録はこれでお仕舞です、次回は第二回です、お待ちください。 第一回語り合い記録を読む
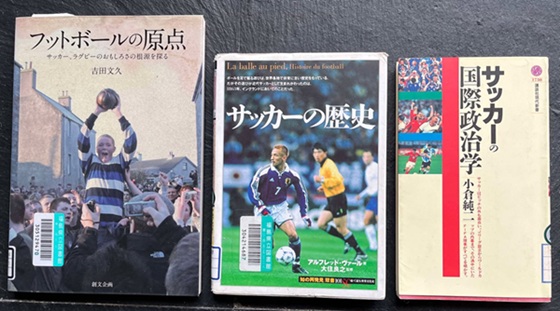
『フットボールの原点─サッカー、ラグビーのおもしろさの根源を探る』2014年1月8日刊行
『サッカーの歴史』2002年1月20日刊行
『サッカーの国際政治学』2004年7月20日刊行
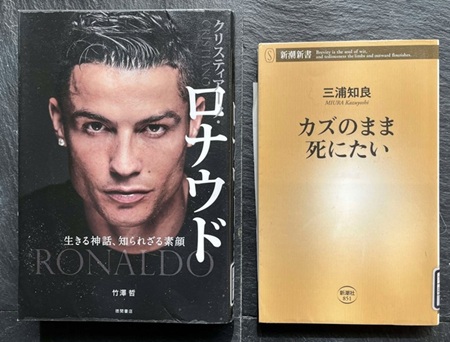
『クリスティアーノ・ロナウド─生きる神話、知らざれる素顔』2028年4月30日刊行
『カズのまま死にたい』2020年2月20日刊行
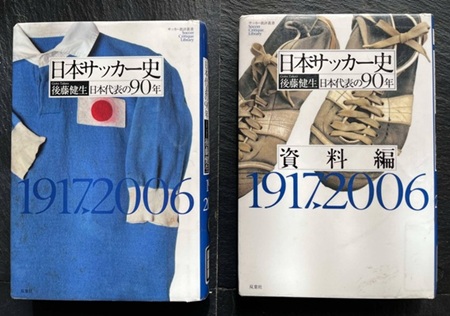
『日本サッカー史─日本代表の90年 1912,2006』2007年1月23日刊行
『同上 資料篇 』刊行日同上