第三のジャーナリズム
花田達朗
作成:佐藤敏宏
2 四つの波頭――私の身の周りで
私が日本におけるジャーナリズムとメディアの関係の潮流変化を肌で感じ、その波頭を目視できる事例が私の身の回りで起こっている。それは「マスコミ」という日本特有の体制がドミナントな磁場の周縁、ないしはその外側で起こっている。
日本「マスコミ」では、普遍的リベラリズムを建前にして、しかし空文と化した諸言説、商業主義と儲け本位主義、政権政党や政府や議会からの政治的圧力に対して順応的な態度(忖度)、情報生産過程における閉鎖的な談合文化などがグチャグチャに絡み合っている。それをせめぎ合いや葛藤と書いてもいいが、しかしそう簡単なものではない。ポリティカル・エコノミーで切ったとしても逃げられてしまう。使う道具が合っていないのではないかと思う。
普遍的リベラリズムを故郷とする西欧型ジャーナリズムは個人の自我をベースとしており、主体と客体の分離に立つ。その上に取材活動と作品内部における「客観性の原則」(Objectivity)が打ち立てられる。下部構造と上部構造の概念もその装置の中に主体と客体の分離を埋め込んでおり、そこに主体を立ち上げてくるし、主体間の利害の対立と交渉の構図が立ち上がってくる。新聞発行者であったり、ジャーナリストであったり、と。しかし、「西欧型の普遍的リベラリズム」と言う時、それは修辞矛盾である。リベラリズムは西欧固有の歴史的経験の中から生まれてきたものであり、それが地球上のどこでも通用するという意味で普遍性を自らに要求するならば、それは僭越の誹りを免れない。西欧型と普遍性は言葉上で両立しない。しかし、その強みは「普遍性」を感じさせるだけの理念的モデルの強さにある。ただし、非西欧(このように括るのは乱暴ではあるが、便宜上)には非西欧の多様な歴史的経験がある。良くも悪くも。そして、そこにはまた多様な思想がある。
他方で、日本型「マスコミ」では主体は不問にされ、主体の構築は避けて通られる。望まれないし、嫌われる。そこでムラ社会だとか村落共同体だとか言われる。家父長的な性格を濃厚に保ち、「家」(イエ)=「会社」の論理と意識が依然として支配する。実際に、経営も編集も労働組合も一つの「会社」で完結するシステムを護持して、揺るぎない。他の産業と違って日本語障壁に守られてグローバル化にさらされることもない。外の環境からの脅威がないので、旧態依然のままで自己革新が起こりにくい。逆説的な言い方になるが、ここではムラ意識、家父長制、男権主義、軍隊文化などによって構成される上部構造が下部構造の「マスコミ」の生産様式を規定していると言える。建屋と土台の関係がアベコベに逆転しているのだ。それはポリティカル・エコノミーの想定外である。さらには日本型「マスコミ」の実践は世界の他の地域の人々に参考になるような思想やモデルを生み出すことはなかった。
主体の構築が意図されないところでは、客体の対象化が曖昧となるのは避けられない。そこで「権力の監視」という、普遍的リベラリズムを故郷とするジャーナリズムにとっての第一のミッションは実質化されず、せいぜい空疎な標語で終わってしまう。代わりに主体と客体の未分化とか癒着とかいう事態が生じ、そこでは権力の対象化は無理なことであって、機能しないのである。そして、いつの間にか曖昧にズルズルと自らも権力の一部となってしまう。
こうした日本「マスコミ」の強力な磁場の存在がそこにあっても闘ってきた者たちはいる。では、その者たちは何に依拠してきたのだろうか。前に下部構造の変容で述べた、20世紀から21世紀のテクノロジーとエコノミーの変化は、確かに日本でも同様の力でジャーナリズムに影響を与えてきた。しかし、その影響はどこの国であれ、ローカライズされた結果をもたらしてきた。その点だけを見ればグローバルな変化と軌を一にしていると言えるけれども、それだけには止まらない。何に注目すべきか。その情景をミクロな具体的な波頭に着目して見ていくことにしよう。「波頭」というのは、多くの人にまだ注目されないもの、社会的な視界の地平線で動いているもの、立ち上がって境界を越えようとしているものという意味である。それらは私の周辺の、私の目の届く範囲での情景である。今の私は身体への眼差しでしか認識することができない。
(1)『Tansa』――ニュース組織として日本で唯一GIJNに加盟
FCCJ(Foreign Correspondents' Club of Japan)(日本外国特派員協会)での記者会見を終えて、私が部屋を出ようとした時、そこに渡辺周は立っていた。そして「私にお任せください」と言った。2014年9月の「朝日新聞『吉田調書』記事取消事件」を受けて、私はその12月に鎌田慧氏や海渡雄一氏と共に共同記者会見に臨み、記事取消は不当であると批判し、ジャーナリストの立ち上がりを促した。渡辺が私の目の前に現れたのはその会見の直後だった。それから1年4カ月後のこと、渡辺は私の研究室に来て言った。「会社を辞めました」と。渡辺は私が所長を務めていた早稲田大学ジャーナリズム研究所の招聘研究員になっていて研究所に出入りしていた。彼は「会社」を捨てて、身一つになったのだ。私はプロジェクトのミーティングで「渡辺さんが編集長になります」と言った。申し訳ないけれど給料は出せない。ノンプロフィットの組織だが、同時に当初はノンサラリーの組織だった。彼は退職金で暮らした。大口寄付者がいて設立されたわけでもなく、大学から資金援助を受けたわけでもなかったからだ。保障は何もなかった。決意だけがあった。
こうして「大学発メディア」のプロジェクトの責任体制は固まり、一年間の準備をして2017年2月には特集「買われた記事」でネット上にデビューした。『ワセダクロニクル』の創刊である。6月にはGIJNへの加盟申請が承認された。そのメンバーとなったことの意味は大きい。2018年には研究所から独立してNPO法人になり、2021年には名称を『Tansa』(註5)に改めてリニューアルした。財源は毎月の定期寄付金(マンスリーサポーター)、単発の寄付金、財団からの助成金などだ。コンテンツはカネも手間暇もかかる探査報道。広告は取らず、購読制でもなく、記事は誰でも好きな時に無料で読むことができる。記事を収益の対象とはしない。勧進のように事業へのお布施だけでやっていこうというのだ。
渡辺はそういうNPOで理事長を務め、編集長を務めてきた。しかし、彼はあくまで記者であり、ライターなのだ。組織の性格としては「ジャーナリズムNGO」という自己認識に立つ。ノンプロフィットだけでなく、ノンガバメンタルを強調したいからだろう。市民社会のアクターとしての矜持がそこにある。創刊以来、7年間を持ち堪え、8年目に入った。山あり谷ありだったが、私はずっとそれをそばで見てきた。大ブレークを起こすまで見届けたいと思っている。あの時「私にお任せください」と決然と私に言った言葉を渡辺は忘れることはないだろう。
『Tansa』は冒頭に登場したドイツの『コレクティブ』と友好関係にある。共にGIJNを舞台にしたグローバルな運動の一翼を担っている。『Tansa』は潜在的にはどこの国のニューズルームとも国境をまたぐ取材プロジェクトを組むことができるし、その推進を方針に掲げてきた。実際にいくつかのコラボをやり遂げており、海外メディアからは日本のパートナーと見なされている。今年4月にはアジア発のオリジナルな探査報道のストーリーを共同で打ち出していこうと、『Asian Dispatch』が結成された。『Tansa』を含めてアジアの10カ国から18の報道機関が加盟して設立された。本部はインドのデリーにある。国境をまたぐコラボの常態化に向かって事態は動いている。日本の大きさなら、『Tansa』のようなニューズルームが他にせめて五つくらいあってもいいのではないかと私は考えてきた。米国には「非営利ニュース協会」(INN)に加盟する独立非営利ニュース組織が今日、450ある(註6)。日本で重要なことはネット上に独立したニュース組織そのものがもっと立ち上がり、数がもっと増えることだ。ジャーナリストの本懐は取材してニュースを書くことではないのか。他のことは二の次だろう。
創刊以来『Tansa』が探査報道の要に据えてきたのは、「権力の監視」よりも「犠牲者の救済」だった。特集シリーズの「強制不妊」や「双葉病院 置き去り事件」にしても、今も連載中で中川七海が書く「公害『PFOA』」(大阪府摂津市のダイキン工業淀川製作所の周辺地域の汚染)や辻麻梨子が書く「誰が私を拡散したのか」(スマホアプリでの性的画像・動画の拡散と売買およびプラットフォームの不作為)にしても、そこには具体的な犠牲者がいる。権力の不正や不正義や横暴から被害を受け、犠牲となっている生身の傷つく身体がある。「人間の尊厳」を奪われた身体がある。「人間の尊厳」は身体に宿るのである。『Tansa』にとって「権力の監視」とは抽象的なことではなく、まず具体的な犠牲者の救出と救済であり、返す刀で権力を撃つのである。それが犠牲者の「人間の尊厳」の回復につながる。そのために権力の内側に入り、肉薄する。権力の犠牲者の代理人として働くのが「探査ジャーナリスト」(investigative journalist)である。
政治的、経済的、社会的、文化的、技術的暴力の源泉は権力である。身体的、言語的、心理的、性的暴力の源泉も権力である。可視的な暴力と不可視的な暴力の源泉もまた権力である。これらの暴力のすべてを揃えた、極大の暴力こそが戦争である。すべての暴力形態を究極まで最大限に動員するところに戦争というものの特異性、異常性がある。
権力は抽象的な概念であると同時に、しかし具体性あるいは身体性を備えている。権力者は身体を持っている。だから、権力を頭で考えるのではなく、五感を使って自分の身体で権力を持つ人間や組織に肉薄する。こういうやり方で権力の作動とその暴力性を事実によって暴露し、真実を明るみに出し、もって権力の暴力と犠牲者の発生とが繰り返されることを防ぐ、そのための社会的実践を「探査ジャーナリズム」(investigative journalism)と呼ぶのである。その実践が『Tansa』に寄付をするマンスリーサポーターの理解と支持を得てきたし、今それが徐々に広がりを見せている。
渡辺の記事を読んでいると、彼はひたすら現場を踏み、人に会う。成果が上がろうが、上がるまいが、それをやる。しかし、ジャーナリストが身体を動かし、感覚を研ぎ澄まし、現場に立てば、手ぶらで帰ることはない。そのことが、昨年彼の上梓した『消えた核科学者―北朝鮮の核開発と拉致』(岩波書店)によく現れている。今、彼の身体は自由だ。心身が解放されている。だからよく観察することができ、よく言葉を紡ぎ出すことができる。
渡辺は「マスコミ」経験のない二人の若いレポーターを内部で実践的に育成してきた。さらに高校生たちとジャーナリズムを語り、創る場所を大事にしている。高校生のインターン生を採用したり、「自由学園」(「はじめての女性新聞記者」羽仁もと子が1921年・大正10年に夫の吉一と共に創立した学校)やフリースクールに呼ばれて授業をしたりしている。渡辺はそういう場所に身を置き、肉声を交換することが好きなのだ。その時間を惜しまない。渡辺は『Tansa』をジャーナリズムの道場として現代の修業の場にしたいのだろう。道の修行とは身体を通じてしか行なわれない。そのような考え方と動き方をすることが、彼のジャーナリストとしての身体技法であり、所作なのである。

Tansa webへ
(註5)『Tansa』のURLは、https://tansajp.org
(註6)INN(Institute for Nonprofit News)は、2009年にニューヨークのポカンティコ・センターに27人のジャーナリストが集まり、宣言を発して設立された。加盟組織は今日450に達する。それらの組織は、ブログやコメントや評論を発信するサイトではなく、取材してニュースを発信する組織である。加盟するための共通の価値観は、非営利であること、独立した編集、事実に基づく取材、非党派性、放っておけば語られない事実を語ること、探査ジャーナリズム、パブリック・サービス・ジャーナリズム(公衆のために権力を監視するジャーナリズム)、デモクラシーの擁護、財務とガバナンスの透明性、スタッフとオーディエンスのダイバーシティとインクルージョン、協働や同僚間の友愛や相互リスペクトという仕事カルチャーを基礎とすることなどである。これは普遍的リベラリズムの延長線上にあると言えるものだ。非営利という点だけがユニークである。それぞれのニュース組織はローカル、広域ローカル、ナショナル、グローバルなど得意とする守備範囲を持っているが、ローカルをカバーするニューズルームが圧倒的に多い。米国ではネットこそローカルなのだ。INNはメンバー組織に対してトレーニングや運営サポートの提供のほか、組織間のコラボの推進やネットワークの形成を行っている。
設立会合の資金を出したのはロックフェラー兄弟財団など三つの財団だった。設立会合の記念写真を見ると、先のチャールズ・ルイスや『リヴィール』のロバート・ローゼンタールが映っている。二人とも『Tansa』の国際アドバイザリーボードのメンバーを務めてきた。
INNのURLは、https://inn.org
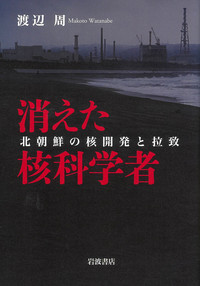
渡辺周『消えた核科学者 北朝鮮の核開発と拉致」(岩波書店、2023年)
(2)『News Kochi』――「ヤメ記者」たちの集結
今年の元旦、依光隆明からメールが届いた。それはローカルニュースサイト『News Kochi』(註7)の立ち上げを知らせるものだった。昨年5月にはその計画を聞いていた。カネのかからないモデルで地域メディアを立ち上げ、今でも「書きたい、書くのが好き」という辞めた新聞記者たちを集めて、一緒に書く場所を作りたいということだった。2022年3月に朝日新聞諏訪支局長を最後に13年間の朝日新聞での単身赴任生活を終えて、同時に40年間の新聞記者生活に区切りをつけて依光は妻のもとに戻り、生まれ故郷の高知でそういう計画を練っていたのだ。
早速、サイトをクリックしてみて驚いた。依光を含めて高知新聞が多数だが、愛媛新聞や共同通信を辞めた新聞記者たちを9名もメンバーとして集めている。巷には元検事で弁護士に転じた者を「ヤメ検」と呼ぶ言葉がある。その俗語に倣って言えば、これは「ヤメ記者」たちが立ち上げたニュースサイトだ。特徴を次のようにサイト上で謳っている。
「特徴は、できるだけニュースを柱にすること。オピニオン(意見、論)は頭で作ることができるが、ニュースはファクトを掘り出さないと始まらない。ファクトを掘り出すには労力もかかるしカネもかかる。そうやって掘り出しても、おそらく多数の人に読まれるわけではない。だからこそあえて誰かがその役割をする必要がある、という考えのもとに新聞記者経験者が集まった。」
足で事実を取材してストーリーを書くニューズルームだということを宣言しているのだ。控え目な表現だが、そこにはプロにしかできないことがあるという矜持が見てとれる。ブログやコメントは自分で取材しなくても書ける。SNSのみならずテレビも新聞も「オピニオン」で満ちている。同時に、今どきの新聞によく見られる「コタツ記事」にも異を唱えているように聞こえる。取材して掘り出したファクトを書くというニュースの原点に立つ、その旗を掲げたのだ。財源は寄付と広告としている。
依光は高知新聞で社会部長を務めるなど社会部記者のエースだった。マスコミ業界でいう「調査報道」(記者クラブに依存しない報道、発表報道でない報道ということ)の強化の必要性を感じた朝日新聞のトップに請われて、依光は2008年に朝日新聞に移った。少なくともその時のトップは見識とポリシーを持っていたということだろう。トップ次第でメディア組織はどっちにも転ぶ。それは東日本大震災の3年前だった。大震災が起こった時、依光は特別報道部長に就いていた。3・11以降、日本「マスコミ」は記者が現場から逃げたとか、大本営発表の垂れ流しだとか轟々たる批判にさらされていた。その中で依光は「プロメテウスの罠」という名前の連載企画を立ち上げ、チームを率いた。記者たちが現場で取材した記事が毎日掲載された。原子力災害で被災した福島の人々が熱心に読んだ。もしも「プロメテウスの罠」がなかったなら、大震災報道はジャーナリズムとして壊滅的だったと言われたことだろう。
2017年から5年間、依光は諏訪支局で一人になって一新聞記者として仕事をした。2022年に退職してから『世界』に寄稿した「ジャーナリズムはどこに息づくか」(註8)を読むと、その様子がよくわかる。諏訪で、「行政も、議会も、町内会も一つの流れに乗って進むとき、流れに疑問を呈する住民は孤立する」、そういう現場を目の当たりにして、「しぼみそうになる声を拾い上げ、ときには住民に成り代わって国や自治体に質問するのが新聞だ」という想いを深め、それを無心に実践した。依光は大学教員にもならず、コメンテーターやメディア批評家にもならず、どの場所であれ記者としての身体をそこに置いて一貫して書く。それが天職なのだ。そのことを今度は「ヤメ記者」を集めて『News Kochi』でやっている。
会社を辞めて「安全地帯」に身を移したあとで元の古巣の「マスコミ」を批判する人たちがいる。何か勘違いをしているのではないか。そんなことをしてもリスクを取ったことにはならない。在職中にどれだけのリスクを取って、批判すべき事態を変えようとしたかが問われる。そのような辞め方は辞めることの「美徳」の中には入らない。それは新しいジョブを得て、転職したということにすぎない。依光はそんなことはしない。会社を退職したあともリスクを取って記事を書き続ける。自分がかつて居た「マスコミ」を批判するではなく、自分が今見ている権力を批判する。
日本「マスコミ」は縮小再生産の真っ只中にある。人件費のカットと人材の流出が相まって、「ヤメ記者」はどんどん増えている。それは「マスコミ」という幕藩体制の終わりの姿だ。開国に向かわなければならない今、会社を辞めた脱藩浪士の役割は大きいのではないか。明治憲法をどうするかで起こった自由民権運動でも「ヤメ侍」は役割を果たした。依光には「ヤメ記者」が集まったら何かできるという確信のようなものがあった。その心情は郷里土佐の文化なのかもしれない。
『News Kochi』の創刊以来、依光は次々に記事を出している。「県発注工事で談合疑惑」のシリーズで県庁をまな板の上の鯉としたかと思ったら、今度は「高知市による民有地占拠疑惑」のシリーズで被害者に代わって市当局を問い質す。合間には単発で「惜別 土佐沖で特攻、叔父たちの青春を追った土田彰さん」の記事を発信する。読ませる味のあるストーリーテリングである。まさに、「自分が書かなければ表に出ないことを書く」ことを通じて、ジャーナリズムの地方からの再生を実践している。
依光も考えているが、私は各地に散らばる「ヤメ記者」たちがそれぞれの場所で『News Kochi』のフォーマットを借りて、ローカルニュースサイトを立ち上げれば良いのではないかと思う。そして、できればネットワークを組む。それは、前回述べた米国のINNへの道だ。INNはリーマンショックの翌年に生まれた。なぜか。多くのローカルプレスが潰れたり、身売りしたりしたからだ。たくさんの記者が解雇された。結果、ローカルの空間に「権力の監視」の空白地帯が生まれた。それが拡大し、各所で権力の濫用や汚職の増加が目につくようになった。その因果関係を証明する実証的研究論文も出た。プレスのプレゼンスがなくなった時、何が起こるのかをそれは示していた。その事態はデモクラシーにとっての危機と捉えられた。ネット上に非営利のローカルニュースサイトやコミュニティニュースサイトが雨後の筍のように立ち上がってきたのはその危機感を背景にしていた。その中心には「ヤメ記者」たちがいた。INNはその情況に対応すべくリーダーシップのあるジャーナリストたちによって設立されたのだった。そういう米国の情況と、依光が「近年、公権力と報道機関との関係は急速に一方へと傾いたように思う。強さが増す権力側と、弱り続ける報道側という構図である」と書いた日本の情況とは、どこか似ているのではないか。
依光が退職したあと、朝日新聞は諏訪支局を廃止した。発行部数が落ちる中で20年以上も前から始まった、読売新聞を除く全国紙の地方からの撤収はますます加速している。諏訪およびその周辺地域の住民たちは依光というスーパー書き手のみならず、一つの全国紙のプレゼンスまでも失ってしまったのである。住民たちは辞める依光に「あんたがいなくなると、怖い」と言った。先の『世界』の論考の冒頭で、依光はそう書いている。私は、2020年秋に彼を諏訪に訪ねたが、その時に会った住民たちや彼の記事の読者たちの顔を思い出さずにはいられない。

(註7)『News Kochi』
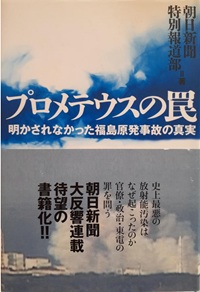
朝日新聞特別報道部『プロメテウスの罠: 明かされなかった福島原発事故の真実』(学研プラス、2012年)(これを第1巻として第9巻まで出版された)
(註8)依光隆明「ジャーナリズムはどこに息づくか」『世界』、第960号、2022年8月号、74-85頁。
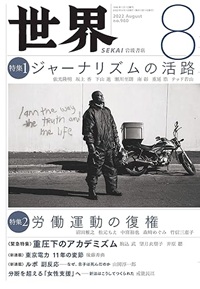
『世界』960号
(3)映画『生きる』――犠牲者と共に創る
フレッシュネス・バーガーの店の椅子に座って、私は寺田和弘と向き合っていた。その日は何の話かと思ったら、彼が「大川小学校のことで映画を撮りたいです」と言った。2021年4月のことだ。
私も2011年の東日本大震災のあと、10月に教育学部新聞学ゼミの学生たちと共に宮城県石巻市の大川小学校の校門の前に立ち、献花台で手を合わせた。津波に飲まれて児童74名(うち4名は行方不明)と教員10名が亡くなった。校庭の向こうには手の届くような距離に裏山の傾斜地が目に入った。そこを駆け上がればよかったのに、「なぜ?」と思った。児童は教員の誘導で山ではなく川の方向へ向かい、津波に巻き込まれた。同じ日に同じように津波に襲われた福島県浪江町の請戸小学校では近くの小山に避難して児童全員93名が助かり、他方大川小学校では多数の児童が犠牲になった。なぜ子どもたちは学校で死ななければならなかったのか。
寺田は映像プロダクションのパオネットワークのディレクターで、NHKや民放のテレビ番組の仕事をしてきた。また、ドキュメンタリー『アイヌの誇り』を一人で制作してYahoo! JAPANクリエイターズにアップしたりもしていた。その作品は、科学者に勝手に持ち去られた先祖の遺骨の返還の要求や先住民としての漁業権の要求などをテーマにした鋭いものだった。その寺田にとって映画の監督は初めてだった。彼はテレビの外に出て、テレビでは出来ないことをやろうとしたのだ。そこに私は惹かれた。
映画メディアにはその下部構造がある。資金調達と配給宣伝だ。フィルムだけ創っても動かない。私は知り合いの二人を寺田に紹介した。クラウドファンディング運営会社MOTION GALLERYの大高健志氏と配給会社「きろくびと」の中山和郎氏である。2021年7月にスタートしたクラウドファンディングは、4カ月間に317人のコレクターから総額460万1000円を集めた。2022年に完成した映画『「生きる」
大川小学校 津波裁判を闘った人たち』は「きろくびと』によって全国の映画館に配給され、一般公開された。作品は2023年第78回毎日映画コンクールドキュメンタリー映画賞などを受賞した。自主的に上映会が各地で組織され、上映は今も続いている。
この映画の主人公は、犠牲となった児童の親たちである。国家は失敗して間違えることがある。ならば責任を明らかにして、その責任を認めてほしい。しかし、当局は非を認めない。「国家は間違えない」という神話になぜそれほど固執するのか。親たちは自分たちで撮影して記録を残していた。市教育委員会の保護者説明会での質疑応答のシーンや、親が実際に裏山を駆け登って、それにかかる時間をストップウォッチで測定したシーンなどである。映画ではそういう映像を取り込んでいる。映画のある部分では遺族の自主制作映画の趣さえある。寺田による親たちへのインタビュー映像は「国家に向き合う市民」という意識の成長の記録である。母親の言葉が逞しさを増していく。ある父親は、何がつらいかと言って、裁判のために自分の子どもの命に値段をつけなければならない、こんなつらいことはないと語った。それでも訴訟を起こした犠牲者の親たちはバッシングを受けた。「お上」に逆らったからだろう。
別の主人公は吉岡和弘、齋藤雅弘の両弁護士だ。犠牲者の無念さを我が事として、代理人という存在以上になって真実の解明に打ち込んでいく。難しい損害賠償請求訴訟で勝訴に持ち込む。2019年に最高裁は石巻市と宮城県の上告を棄却し、学校の防災対策の不備など「平時からの組織的過失」を認めて市と県に遺族への賠償金の支払いを命じた二審の仙台高裁判決を支持し、同判決が確定した。
しかし、原告遺族は勝訴によってであれ、救われはしなかっただろう。原告勝訴を受けたあとの被告当局の言動や行為を見ても、責任が果たされたと認めることはできなかったであろう。遺族たちはこの映画を寺田と共に創ることによってはじめて救われたのではないだろうか。遺族たちの身体は映画の主人公として、その存在感が映像や音声に表現され記録されている。そこに寺田の手腕がある。
寺田は弁護団から映像制作を持ちかけられた。最高裁判決のあと遺族への脅迫事件があって、弁護団は原告遺族の想いが社会的に広く理解される必要性を感じ、寺田に打診したのだ。当初の映像制作のアイディアは一本の映画作品の製作へと発展した。全国の映画館や上映会場には上映後に登壇して、観客に語りかけ対話する原告遺族、両弁護士、そして寺田の姿があった。
2020年に寺田を私に紹介したのは小林篤だった。彼は『足利事件─冤罪を証明したこの一冊の本』(講談社文庫)の著者である。その10年前に小林を授業に招いた。私はその身体を眺めながら、ユニークな授業に耳を傾けた。その小林に寺田はどこか共通するものがあった。「器」とはよく言ったもので、「ジャーナリストの器」というコトバが頭に浮かんできた。「器」とは身体にほかならない。
「映画『「生きる」 大川小学校 津波裁判を闘った人たち』の予告編(YouTube)
(4)地平社――結社主義への転身
編集者を乗せたホンダのアメリカンモデルのバイク、STEED400が田園を走る。ソロでツーリングする熊谷伸一郎は何本の地平線を見てきたことだろう。ランドスケープを眺めては、その一部となって身を置く。頭を空っぽにしながらも、時にはジャーナリズムの景観についても思いを馳せただろう。自分はそのどこに身を置くのかと。
依光が『News Kochi』を創刊した同じ月に、熊谷は「地平社」を創業した。その時、47歳。出版のメッカ、神田神保町に事務所を構えた。岩波書店からの退職金を資本金にあてた。4月には一挙に6点の書籍を刊行し、6月には月刊誌『地平』を創刊した。焦点をジャーナリズムに合わせている。
入居したての事務所に私を招き入れた時、熊谷は私に言った。「地平社の『社』は会社の『社』ではなく、結社の『社』です。ここでの社員は会社員の社員ではなく、結社の『社員』です」と。なるほど、結社としての出版社。結社は西欧近代のとば口に登場したプレスの原点だ。西欧近代の歴史的経験において、憲法にいう「言論表現の自由」と「結社の自由」は結びついている。「結社の自由」にいう「結社」のメインは一つには労働組合だが、より古くは言論結社だ。個人および同志的結合を基礎にして言論表現活動は行なわれたが、そこに国家は介入してはならないと、国家に禁止命令をしたのが憲法のそれら自由権の条文だった。結社とは英語で言えばアソシエーションで、その「社員」はアソシエイト。熊谷は四人のアソシエイトとともに地平社を立ち上げた。その全員が脱藩浪士なのだ。「ヤメ編」というべきか。パブリッシングの世界もまた動いている。
熊谷は岩波書店が発行する月刊誌『世界』の編集長を2018年7月から22年9月まで4年ちょっと務めた。その在任中に「3年連続で販売部数・定期購読部数を伸ばすとともに、調達見直しや残業削減などの改革も進め、同誌の刊行を維持する」と自身のプロフィールにも書いている。そう書けるだけの実績と矜持、そして『世界』という媒体への想いが熊谷にはあった。ところが、2021年12月、会社から営業局への異動を提示される。ということは、編集長の解任だと誰でも受け取る。しかも、その理由の説明がない。よほど組織の歯車にでもなっていない限り、誰であろうと承服はできないだろう。ましてやコミュニケーション企業の中でのことであり、社会的フェアネスやディスカッションの増進を社会に向かって訴える総合雑誌の編集長(Editor in Chief)の人事である。熊谷は経営側に合理的な理由の説明を求めた。が、埒があかない。
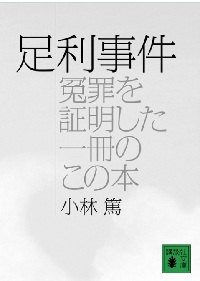
講談社Book倶楽部
「内部的メディアの自由」と「編集権声明」
その事態を漏れ知った時、私の頭に浮かんだのはドイツ生まれの「内部的メディアの自由」(Innere Medienfreiheit)という概念だった。そのテーマで本を編み、論文を書いたことがある(註9)。ドイツではかつてその概念にもとづいて「編集者綱領」(Redakteurstatut)を制定しようというジャーナリストたちの運動があり、実際にそれを定めている新聞・雑誌社が存在するし、西部ドイツ放送協会など公共放送協会の中には州の放送法でその制定が義務づけられているところもある。「編集者綱領」にいう、ドイツ語の「編集者」=Redakteurとは出版の編集者だけを指す言葉ではなくもっと広い概念で、記者、ジャーナリスト、編集者、番組制作者などジャーナリズム作品の制作に携わる職能人のことを指す。通常「メディアの自由」という時、メディア組織の外部からの干渉の排除を意味するが、「内部的メディアの自由」とはメディア組織の内部で仕事をする「編集者」の自由、つまり経営に対する「編集の自由と自律」や「編集の独立」のことを意味している。「編集者綱領」は各企業の経営側と「編集者」代表委員会との間でいわば職場協定として締結される。規定の中には、例えば編集長の任命や解任における提案と同意などのルールや、両者の間で紛争が生じた時の解決手続きなどが定められている。もしも岩波書店に「編集者綱領」があったとしたら、熊谷の編集長更迭の人事はどうなっていただろうか。そこで現れるであろうことは「慣行」の不安定さではなく、事前の合意文書で定められた手続きの力なのだ。こういうやり方を「手続きによる民主主義」という。
「内部的メディアの自由」の概念は、仮にその必要性に共感できたとしても、この国では現実とうまく噛み合わない。まずもって日本「マスコミ」は日本新聞協会の「新聞編集権の確保に関する声明」(通称、「編集権声明」)の傘の下にある。これは占領期の1948年に新聞労働運動を抑圧するためにGHQの指導のもとに導入されたもので、「編集の権能」(これを「編集権」と短縮するのは元来、適切でない)は経営側にあって労働側にはない、その権能に従わない者は何人といえども排除すると宣言している。つまりこれは「内部的メディアの自由」を否定しており、これが今も廃止されずに生きている。新聞社のみならず、通信社、NHK、主要民放も新聞協会の会員社であり、そこにも声明の効力は及ぶ。また、その会員社であることが「記者クラブ」という情報カルテルのメンバーの資格である。つまり政府や警察などの官公庁が「記者クラブ」しか相手にしないのは、「編集権声明」という担保があり、クラブの記者たちは「安全安心」だからなのだ。
各種の業界制定倫理綱領が日本「マスコミ」のオモテの憲法だとすれば、「編集権声明」は共通のウラの憲法だと言える。新聞界では1946年制定の新聞倫理綱領を2000年に改訂し、新倫理綱領を制定した。その際に、「(編集権声明は、)倫理綱領と同様、時代の変化に合わせて、部分的にせよ、見直す時期に来ていると私は考える」(註10)と主張した経営者側の賢人がいた。廃止すべきだと言わなかったのは残念であるが、その「見直し」という方向性ですら新聞協会理事会で議論されることはなく、ウラの憲法はそのまま存置された。労働組合側にそのような指摘をする賢人がいたということは寡聞にして知らない。それを廃止しようというジャーナリストや労働組合の運動はついぞ起こることはなかった。
「編集権声明」はその導入時には、経営者の戦争責任を問い質したり、「編集の独立」を主張したりして闘った新聞労働者の運動を標的にしたものだったが、高度経済成長期には日本的経営法の会社主義の大黒柱へと役割を変えた。会社主義に取り込まれたメディア企業の企業内労働組合は「編集権声明」がもともと労働組合に矛先を向けていたことさえ忘れて、存在を許してしまったようである。日本には「編集権声明」に反対する運動を組織すべきジャーナリストや編集者や番組制作者が個人で加盟する職能組合(ジャーナリスト・ユニオン)は存在しない。
いずれにせよ、「編集権声明」の存在を不問にして「内部的メディアの自由」を論ずることは意味のないことだ。「編集権声明」の存在を放置したままで「内部的メディアの自由」や「編集の独立」などあり得ないからだ。しかし、日本「マスコミ」の経営側も労働側もこのGHQ時代の遺産に手をつけないという態度では一致している。この問題に関しては占領期の見直しと主権回復後の再編成は着手されないままになっているのである。むしろ放置されてきたのである。このまま行けば、日本「マスコミ」の終焉とともに「編集権声明」は失効となるのかもしれない。それは喜ばしいことだろうか。日本「マスコミ」の終焉を座視するのでないのなら、内部から「編集権声明」廃止の要求とメディア産業労働組合またはジャーナリスト・ユニオン結成の運動が出てきても良いのではないかと私は思う(註11)。無理かもしれないが、闘いがあるかないかは、「マスコミ」終焉後のジャーナリストの世界を少なからず規定するからである。
(註9)花田達朗編『内部的メディアの自由―研究者・石川明の遺産と継承』日本評論社、2013年。同書に私は「『内部的メディアの自由』の社会学的検討―理論と現実の日独比較の視点から」という論文を書いた。これに労働組合側から関心を示されたことは一度もない。

花田達朗編『内部的メディアの自由 研究者・石川明の遺産とその継承』(日本評論社、2013年)
(参照:日本新聞協会「編集権声明」)
(註10)中馬清福「新『新聞倫理綱領』制定にあたって」『新聞研究』、第589号、2000年8月号、14頁。その時、中馬は朝日新聞社代表取締役専務取締役編集担当。この論考が出るより前に私は中馬と話したことがある。中馬は朝日新聞社上層部の中のジャーナリズム派の1人だったと私は位置づけている。やがてジャーナリズム派は1人また1人と立ち去り、跡には官僚派が残り、その情況の中で2014年の「朝日新聞『吉田調書』記事取消事件」は起こったというのが私の見立てである。私は日本「マスコミ」の中のジャーナリズム派の何人かと知り合ったが、朝日でのその1人、中馬清福はその事件のあった年末に信濃毎日新聞社の元・主筆として79歳で亡くなった。
問題の公然化、結社への脱出
熊谷は管理職だったので、企業内労働組合の岩波書店労働組合の組合員ではなかった。これは日本では一般的なことだが、しかし日本特有のやり方だ。ドイツでは編集局幹部もジャーナリスト・ユニオンに個人で加盟する。「一人で闘うのか」、熊谷は自分一人に関わる問題だとは捉えなかった。問題の何であるかを他者にも共有してほしいと考えた。熊谷は事態を打開するために出版労連の中にある「出版情報関連ユニオン」(以下、出版ユニオン)の管理職支部に個人で加盟した。「出版ユニオン」(註12)は小さいが、「産業労働組合」の原理の組織だ。これが労働組合というもののあるべき組織原理だと、私は思う。日本の企業内労働組合という組織の仕方は世界的に見れば特殊なものである。企業内従業員代表委員会と言ったほうが正確なのではないか。日本で「労働組合」と呼んでいるものは、ドイツのBetriebsrat(職場評議会)に近い存在だと言っても良いだろう。
出版ユニオンは直ちに会社側に団体交渉の開催を申し入れた。これで事案は熊谷が一人で抱え込む問題ではなく、パブリックな問題となり、いわば公然化された。すなわちコミュニケーションの場ができたのであり、問題情況の可視化と共有化が可能になったのである。コミュニケーションが可能か不可能かはやってみなければ分からない。それと同時に彼の身体は問題の当事者としてさらされることになっただろう。これを個人の問題として見なす視点からは、熊谷の試みは共感されず、傍観されただろう。身体が様々の視線に揉まれたに違いない。何回かの団交の末、引き継ぎを十分に行なうため異動の発令を半年延期することなどを条件として交渉は決着した。
団交で妥結した時か、編集長を解かれて営業局に移った時か分からないが、ある段階で熊谷は会社を辞めて、「ヤメ編」を集めて自分で結社を作ろうと決意したに違いない。そうやって「内部的メディアの自由」がテーマとされない空間から脱出することを、彼の身体が熊谷に求めただろう。そして、結社では構造上、「内部的メディアの自由」の問いを立てる必要もない。経営と編集の分離はないからだ。これは1人のエディターに起こった出来事ではあるが、大きな流れに関わっていると私には思われる。
今日、日本各地で「ひとり版元」が生まれ増えている。出版産業の生産-流通-消費の過程では、著者-版元(出版社)-問屋(取次)-小売(書店)-読者の間で商品・情報・カネのやり取りが行なわれている。この版元を一人でする人が増えている。それが以前よりもやりやすい条件がこの間に整ってきたことが背景にあると見られる。その一つが「版元ドットコム」だ。小規模の版元が大手取次を通さずに(通せずに)本を流通させるには当面、三つのルートがある。以前からある「地方・小出版流通センター」、書店との直接取引、それらに加えて版元ドットコムと連携するトランスビュー方式による直接取引の代行である。これは版元が注文を受けてから出荷する「注文出荷制」を代行してもらう仕組みだ。版元ドットコムのサイトに「版元日誌」という会員のブログがある。これを読むと面白い。「ひとり版元」たちの想いが伝わってきて、私にはそこに一人ひとりの身体性が見えてくる。新聞記者を辞めて「ひとり版元」になった人もいることを私は知った。
結社に集結した「ヤメ編」やソロ活動の「ひとり版元」など、身体性に立った、言論・編集・出版の自由の実践過程のアクターたちが、この国のジャーナリズムの景観を作り、地平を広げていくのではないかと私は思う。
「3 身体に発することば」へ続く
(註11)花田達朗「関西生コン弾圧と産業労働組合、そしてジャーナリスト・ユニオン(3)」『世界』、第951号、2021年12月号、212-221頁を参照されたい。
(註12)出版ユニオンはウェブサイトで次のように自己紹介している。これを読み、私は感動した。これは個別企業の枠を超えた「産業労働組合」の姿であり、これが本来の労働組合だ。非正規労働者と正社員を区別せず、共に組合員として迎えている。あとは包括的な賃金労働協約の締結主体になることだが、そこまでの道はとても遠い。
「出版情報関連ユニオン(略称/出版ユニオン)は、出版(出版社・編集プロダクション・取次・書店・販売代理店など)・印刷・情報・メディア関連ではたらく人のための個人加盟の労働組合です。誰でも、一人でも入れます。会社での働かされ方に納得がいかない、解雇(雇い止め)をほのめかされて不安を抱えている、もっと仕事のスキルを身につけたい、業界の情報をもっと知りたい、と考えているすべての人のための労働組合です。契約社員、派遣社員、パート・アルバイトなどの非正規労働者も正社員も加入できます。」
日本の産業構造では、中心に少数の大企業群があり、周縁に多数の中小零細企業群が存在する。他方、日本の労働組合の構造では、中心に個別企業ごとに正社員が加盟する企業内労働組合群があり、周縁のまた周縁に個人加盟の産業労働組合が存在する。それらは小さく、数は多くない。その中でも賃金労働協約の締結主体となっているものはさらに少ない。この二つの構図が重なった情況では、資本と労働の対等な交渉関係に近づくことは無理で、したがって労働分配率は上がらず、賃金も上がらない。企業内労働組合なので、ストライキを武器にして会社経営者と戦うことはできないし、しないからである。
異常なことに、日本では「連合」(Japanese Trade Union Confederation: JTUC)が闘わずに、政府にお願いをして賃金を上げてもらう。そこで、労働組合の票が欲しい政府がお願いされた形をとって市場の問題に口を出し、賃上げの音頭取りを演じる。「春闘2024」では、岸田政権の意向を受けた「経団連」(Japan Business Federation)が傘下の大企業に賃上げを奨励して、大企業の経営者たちは自分の企業の中の労働組合の賃上げ要求に対して100%の満額の回答を出した。この100%の満額回答が大企業で次々に出される。しかし、これは労働組合がストライキを決行して獲得した結果ではない。しかも、その組合要求の賃上げ率は最初からインフレ率を下回るものであり、たとえその要求が満たされたとしても実質賃金は下がるという水準の要求でしかない。さらに、この回答シーンは日本の企業群全体のうちの氷山の一角、トップ企業のことでしかない。これは、大手企業の間の「談合」を背景にした見せかけの競争入札を思い起こさせる。実に奇妙な光景である。資本主義的でもなく、自由市場主義的でもない。一体、何主義と呼んだら良いのだろうか。とりあえず、「『ムラ社会』主義」とでもしておこうかと思う。手っ取り早く言えば、「政・労・使の談合のエコノミー」である。「連合」は癒着した関係を対等に近づいた関係と取り違えてはならない。
中堅企業群や中小零細企業群の労働者は賃上げから取り残され、低賃金が続く。こうして日本の格差社会は、貧困層の増加を伴いつつ固定化されていく。