■ はじめに
チラシには「言葉が心を紡ぐ家族再生の物語」とあった。現在、壊れてて再生の要る家族とはどんな姿をしているのだろうか。時代状況が変わろうと、人にとって家族は社会の門のようなものだから、家族間に発生する問題は尽きないし目を離さないほうがよい。
『美晴に傘を』はどのような問題をえがき示すのだろうか。高齢者・佐藤の世代なら、家業を継ぐ後継者問題だったろうか、そのときに起きた親と子の意見の相違。さらに地方が都市化の激流に飲み込まれうまれる問題が主なテーマだった。社会と家族の間に押しつぶされるかのように、若者たちが心を病み、あるいは犯罪に巻き込まれてしまう、その姿を描いた作品に出会うことが多かった。
思い出すままに書くと、立松和平原作の『遠雷』。根津甚八が好演した『さらば愛しき大地』のような作品で、45年ほど前の地縁が崩壊する地方にあらわれる若者の姿を、赤裸々に描いていたので記憶に残っている。1970年代の社会と若者たちの苦悩は都市への乾きと拒絶だった。2作品を鑑賞すると50年前の日本における地方の姿を思い出すことだろう。
動画は遠雷を語る立松和平
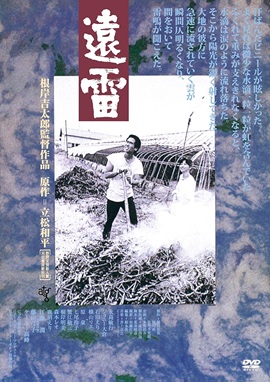
1981年作 ポスターwebより
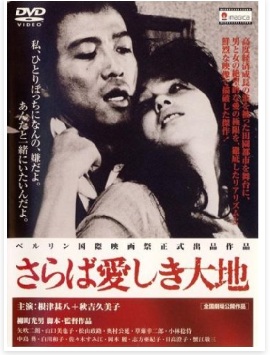
■55年後、2025年の家族
『美晴に傘を』の上映は『遠雷』や『さらば愛しき大地』から約半世紀たっている。遠雷の著者である立松和平がえがいた半世紀前の若者を善次として観ると、登場人物の相関は理解しやすい。
吹き荒れた全共闘運動は「あさま山荘事件」までいきつき、敗北した若者は全国各地に離散し、ひっそりと暮らす者、あるいは闘争運動に力を発揮しその後、会社経営をし社長の椅子を確保し資本家になったものなど、多様な元・若者は日本列島にゴロゴロ生きていて、鑑賞者の身近にもいるはずだ。
善次・老人は全共闘運動に参加したのか?前歴は描かれない。寂れた漁師町でウニ漁にかかわる一人船主で、地域の人々と共に海を生活の糧にしている。仕事のあとは居酒屋で一杯やり、家で友人と呑み、楽しみは呑むことのような暮らしをしている。
『美晴に傘を』に登場する主役は美晴だ。彼女は善次の息子、光男の長女である。彼女は聴覚過敏と自閉症をもつ、という設定だ。美晴の家族は父・光男が亡くなったので、母と姉妹の三人暮らしになった。美晴家族は何処で暮らし、何を生計とし生きていくのかは描かれない。が、父の故郷の停車場の吊り駅名に「余市」とあったので、北海道新聞の本社、札幌市で都会暮らしをしている家族として佐藤は受けとめた。光男は新聞社の校閲係を担いながら、詩人を目指し若くして死した。彼は父・善次に認められない詩人のままで亡くなった。
全共闘世代の老人たちは敗北したわりには、自我が強いのだろう、息子の職業にいちいち口出しするウザイ人である。そのうえ息子との交流を絶ち、漁師になり「おれ以外の輩はみなダメだ、認めない・・・」孤立こそが勲章と思い込んでいる気配もある。映画では料理、出来合いのパンバーグにマヨネーズをかけ酒の肴にする、貧食生活を脱しようとしてない、自業自得の貧しい暮らしを選ぶ老人に見えた。日本列島にごろごろ居そうな頑固爺さん、一人という設定。漁師なら毎夜、刺身を肴に一杯呑むのだろうが、設定がずれている。
■理解できなかった内容あれこれ
(1)
父と息子とはいえ絶交つづきで20年経て、嫁が夫の実家に遺骨をもって突然現れる.。押しかけられた義父・善次(独居老人)だって、一人暮らしのルーティン生活が確立しているなか、息子の嫁と孫に合流されても居心地が悪いどころか、生活の場を奪われ、壊されていく、そういう不信と怒りが沸きたつのではないだろうか。
(2)
自称詩人の息子を拒絶するのは、善次の世間知らずによる原因だろうが、詩人は稼げない、だから暮らしがなりたたない、だから息子を否定する、それはいかにも狭量だ。現金収入をえらうために新聞社に勤めているのだから問題ないはずだ。金を稼げる仕事を目指さない若者を嫌がる、息子の思いに冷や水を差し続けた老人として描こうとしたのか。老人は狭量で害だと決めつけるほうが万民に受け入れてもらえる、と想定するのは間違いだろう。この設定は制作者自身の思考の枠を狭めるだろう。校閲係をして家族4人と生きたのだから、詩人の姿を思い出語りで登場させるだけではなく暮らしぶりも含め息子に投光し物語を紡いでもよかったのではないか。
(3)
自閉症に関しては今は社会制度不備だ。家族で悩んで解け、と決めつけているように見えてしまう点は問題だろう。障害について根気づよく家族どおし関係者と対話を重ね続けることが家族やひとを鍛えるはずだ。ひとは変化しつづけるので対話の継続を欠くと先の見通しは暗い、という思いを醸成してしまうだろう。障害に関する問題は暗く重たいと決めつけず、明るく対話することにしたい。暗く話し合ったら解決するわけでもないし、家族内に障害をもつことは暗いことでもない。そう思うなら近代の優生思想に毒され過ぎたおとなだと自覚したほうがよいし、制作者もそういう人達なのかもしれない。
(4)
社会も家族も障害者を忌避することは、障害を持って生まれた者への人権無視だし、暴力的破壊者としてし理解は進んでいる。トランプ2.0が吹き荒れているので逆戻りする可能性があるけれど、障害をもつことが生きる負担だと決めて描けば、一般の人々は目をそむけ、素知らぬ顔をし暮らし、この世は解決策を手に入れることはできない。
また自身が障害者にならない、とは誰も言えない。だから社会知として障害者対策や支援策などの実装備をすすめるのが知恵というものだ。映画のなかのような家族の問題として閉じずに、開く努力をし語り合うべきだろう。
(5)
『美晴に傘を』は障害者をもつ家族の心的解決を、言葉をもって解くことを主に描いていて、社会策の解決の一つを手に入れるための提案姿勢はみうけられなかった。この点は問題だろう。
■物語の筋をおって
最初の画像は美晴の二つの眼からあふれる涙2粒の大写し。「涙は世界一小さい海」と詩作したのはマルチ表現者の寺山修司だ。美晴の左右の小さな海はどのような大海原に合流するのか、水蒸気になって消えるのか、描かれる「二つの涙」を観ながら、この涙の仕舞かたが映画の見せ場だろうと想像した。仕舞に辿りつくまでどのように物語は展開するのだろうか?この点はこの映画の肝だと想った。
はじまりはこうだ。美晴の家族は夏のある日、さびれた駅(余市)に到着する。そこは美晴の父の実家がある小さな漁師町だった。美晴たちの目的は父の49日に合わせ実家の墓に納骨をしに来た。父の実家にはお爺さんが一人暮らしをしていたが、美晴の父は生前(20年間ほど)実家と美晴の家族を交流させず亡くなった。実社会において、交流の無かったお嫁さんが、亭主の納骨のために、パートナーの実家を訪ね、玄関先でいきなり骨壺をさしだし、納骨をお願いすることは想定できない。それが映画の始まりだった。
美晴の父は彼の父親とどのような問題が起きて絶交することになったのだろうか。絶交の理由は明かされぬまま納骨まで進む。爺さんの家に押しかけた美晴の家族は粗っぽく押し入り、納骨を済ませる。
彼らは互いに交際がなかったし、お爺さんと美晴家族は互いの暮らしを支える営み方、文化背景が違うので納骨などおこなえるはずはないのだが、そこはフィクションの御都合主義とでも言えるか、粗っぽく物語は先を急ぐ。
お爺さんからみれば、美晴の家族は「押しかけ家族」のようなものだから、おりに触れて文化摩擦を起こす。感情を育むべき共有すべき基盤構築と、時間をもったことがない。だから互いが、固定概念だけを何の防御もなくぶつけ合う。嫁はこうあるべき、お爺さんはこうあるべきという、その固定観念から互いの家族は脱することができない。だから激突し合うだけで、互いにとって好ましいコミュニケーションのありかたを手探りで構築できない、しているいとまがない。それは年齢と世代によって起こる家族間の問題より乱暴な設定だった。
嫁とお爺さんの文化摩擦の最も大きなものは、納骨に際しての服装だった。土葬か火葬か?でもめたのではなく、納骨に際し喪主の派手な服装。派手にもめたわけでもなく美晴の母親は、夫が好きだったノースリーブで大きな柄のワンピース姿。これが問題だという。地域の人々は当然のように黒づくめの喪服姿。この対比はたしかに状況を的確に表す手法としては面白い。
光男の父親・善次は息子の死、嫁の衣装、孫の自閉症を理解しようとするための柔軟性がなく、嫁の家族の全てを忌避することから物語が始まる。どのように和解するのだろうか、これが映画のテーマなのだろうか、仕舞まで観ると分かるが和解がテーマではなかった。
光男の父は息子との和解、許すこと、会いたかったと言えなかった、ことを告白するがおそすぎる。生きることは、対話をもってその時々を互いに豊かにしようと暮らすことだから、悔やんでもしかたない。漁の仲間関係を豊かにすることで、息子との貧しい関係のようなことを繰り返さないように暮らすしか残された道は無いだろう。
さて結末は二つの家族は和解し合い暮らし始めるのか、それがこの映画の見どころだろうから詳細は書かない。ただ、美晴、母親、爺さん三人のそれぞれの言葉が輪読のような形式で巡り巡ってお仕舞になる。美晴の涙は海にはならず雨粒として描かれたので予想は外れた。
■美晴の聴覚過敏と自閉症について
美晴の自閉症が回復したような物語は涙をさそうのだろうが、佐藤は受け入れがたい。自閉症が回復する病でもあるかのように観客は受け止めてしまうだろうし、自閉症への思考がとまる、そんな懐疑がうかんだ。
映画のなかで、美晴の母親は自分が美晴より先に亡くなったら、美晴は一人で生きていけるのだろうか、だから守ってあげたい、守り続けたい、と願い生きている。
しかし、どんなに悩みつづけようが人の安全保障のような仕組みが日本の社会に備えられなければ、美晴の母の思いは解消しない、悩みの原因を自己に求めてしまう愚かさを犯すことだろう。思考を展開させない母親を描く映画制作者は問題解決を停止してしまうことに無自覚すぎないだろうか。
佐藤は1970年代末、関西で自閉症の長男をもつ知人の家に泊めてもらい、彼ら家族の困難を観ている。どんなに能力の高い両親であろうと、他者による介護支援を定期的にうけいれなければ、目の前の息子を殺傷し一緒に死にたい、と思うぐらいだろう。そしてぞれを実践してしまうかもしれない。殺人者になるか息子を支援し続ける親になるか、それは実は紙一重であり、どちらへ展開するかは両親の体力と気力と経済力の有無、という自己責任に放り投げられたままだ。
美晴は、父親の描いた制作途中の絵本を読み聞かされることで、おりおりの心の乱れを整えることができる。そう描かれていてフィクションの力を充分に活かし父娘の美しい物語に仕上げていた。映画の終盤に沿って記せば、美晴は恋することで母親から自立し生きていくための傘を必要としなくなる。それは誇大なファンタジーなので、実写による身体から離れアニメーション手法が合っているような気がした。
家族が喧嘩し合えるのは仕合わせの一つなのだ、と佐藤は思う。おおいに家族は喧嘩し合う、意見の相違を確認し合うことに努力し暮らす。善次のように長男の嗜好を断罪し対話不全で無視し放置することは、異なる領域を互いが生きてることなのだ、と自覚できる機会を逃してしまう人は多そうだ。現在の若い家族は仲良しを演じることが家族だと思っているかのようだ。
チラシには「言葉が心を紡ぐ家族再生の物語」とあった
映画が仕舞にすすむにつれ、テーマが絶交状態の家族の和解、自閉症の家族と暮らす、独居老人の受け入れ方、故人と家族の在り方など似ているけど違う問題を、さらに映画と演劇の混在をもくろむなど、多くの思いから生まれる言葉をかき集める。だが多くの意欲が空回りすることで、大切な異なる他者との対話を模索する姿は背後に押しやられてしまっていた。
■『美晴に傘を』 登場人物の構成
主役:20才長女 美晴、(聴覚過敏+自閉症)。
準主役:美晴の母親(透子)専業主婦か?
亡くなり49日の父親(光男・詩人、新聞社の校閲係)共に50才ほど。
美晴の妹、18才ほど。
小さな町のウニ漁などで暮らす光男の父(善次)80才ほどか。
他の取り巻き
猟師仲間、とその家族、居酒屋の女将、ワイナリーの若き経営者
勝気で世話好きな習字老女先生などだ。