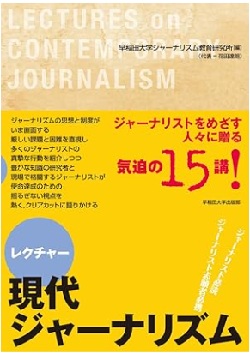大石泰彦著『メディア報道の四半世紀』の刊行に寄せて
─林立する墓標─
大石泰彦は自分自身のことを「気分屋」と評している(本書「解説編」、192頁)。それで、「時々目下の研究の意味が疑わしくなり作業が止まってしまう」と言う(同頁)。ならば、それは「気分屋」というよりもむしろ自己懐疑的と言うべきかもしれない。研究者としての自分の存在および研究という自分の行為の意味について繰り返し疑問符を付けながら歩いてきたのであろう。そういう大石が意を決して、やるべきタスクとして10年前に自らに引き受け、コツコツと進めてきた仕事がこのほど完成を見た。それは、『メディア報道の四半世紀』という書名のもとに成文堂から本年10月1日に刊行された。
著者は1961年生まれで、現職は青山学院大学法学部教授である。
本稿は同書に対する、ごく私的な書評と言えるかもしれない。いや、過ぎ去った過去を振り返る思い出話と言っても良いかもしれない。これからそういうものを書いていこうとしている。少し長くなるかもしれないので、前もってお断りしておきたい。

『メディア報道の四半世紀』 成文堂へ
本書の趣旨
まずは、どのような本だろうか? 「事例編」(総ページ数は346頁)と「解説編」(総ページ数は192頁)の2分冊から成る。本の趣旨について著者は、「事例編」の「はじめに」で、「本書は、この国において、この四半世紀(2000~2024年)の間に発生したマスメディア(新聞、放送、雑誌など)の報道のあり方にかかわる諸事例を収集し分類したうえで、それらに対する解釈(解説)を行うものである」(ⅰ頁)と簡潔に述べている。
この文章の中に重要ないくつかのスタンスがすでに明らかにされている。この国の法学者は論文や評論などの書き物において、この国の政治家と同じように、よく「わが国」という言葉を使うが、法学者の大石はその言葉を使わない。そして、「この国」という言葉を使う。これが「客観的」な態度であることは明らかであろう。
また、「マスメディア(新聞、放送、雑誌など)の報道」という表現を使っており、用語の定義のところで、マスメディアについては、「新聞・放送・雑誌など、時々の社会問題・事件を定期的・継続的に不特定多数の人に伝える活動を行う組織」(ⅱ頁)と定めている。つまりマスメディアとは「組織」だと定義している。注目すべきは、本書の中で大石は「マスコミ」という言葉を一切使わないという点だ。そこも多くの法学者やメディア研究者と違う点だと言える。用語に厳密であるべき「専門家」が、無自覚的、慣習的に、ヌエ的な言葉「マスコミ」を使う姿を眺めてきたが、もうそれだけでその人の「専門性」を疑わざるを得ない。「マスコミ」という言葉の一般的使用法を観察すれば、すぐにわかることであるが、その言葉は「組織」も「会社」も「記者」も「制作者」も「媒体」も「内容」も、そのあらゆるものを臨機応変に指示する、日本独特の不思議な言葉である。ジャーナリズムとメディアを弁別しない、そのような言葉を使って「学問」や「研究」ができるわけがない。私自身は「マスコミ」という概念は正しい認識を妨げるものとして棄却してきたが、その癒着した社会的現実とその言葉を許容している社会意識を体現した言葉としてあえて使用する必要がある時は、「日本『マスコミ』」というように、カギ括弧を付けて使用してきた。
本書の内容
次に、「報道のあり方にかかわる諸事例」と述べているが、これだけでは「何をもって事例としているのか」「事例とは何の事例なのか」がなお曖昧である。そこで、収集した事例の「分類」がどのようなものかを見る必要がある。分類とは「類型」に分別することであり、大石は「1事例1類型」という原則を立てている。一つの事例を一つの類型に整理するという原則である。その「類型」は六つに整理されており、それに従って、「事例編」では「集」として、解説編」では「章」として、共通したタイトルで組み立てが行われている。「事例編」の構成は次の通りである。そこに事例の数を付記してみた。
第Ⅰ集 誤報・虚報(事例数217)
第Ⅱ集 取材源との関係(事例数139)
第Ⅲ集 犯罪報道(事例数98)
第Ⅳ集 政治権力とマスメディア(事例数112)
第Ⅴ集 放送の公共性と独立性(事例数147)
第Ⅵ集 メディア企業と記者・制作者・フリージャーナリスト(事例数38)
最近25年間の合計751の事例が収集されている。途方もない数である。よくぞこれだけのサンプルをウォッチしたものだと感心する。それらの事例が六つのグループに分けられた。これは今まで誰もやったことのない、驚くべき仕事である。
「事例」とは何か?
さて、改めてこの「事例」とは何の事例なのだろうか? 「類型」とは何の類型なのだろうか? 大石は、「解説編」第6章の最後、「第5節 展望」を次のような文章で締めくくっている。その文章の中にヒントがある。
「こうした(ジャーナリスト養成)教育制度の設置が、公正な資格制度の創設へと発展し、さらにそれが『企業内』であるか『フリー』であるかを問わない専門職の連合体である『ジャーナリスト連合』の結成へと向かえば、それはこれまで見てきた日本のメディアの諸問題の主病巣をつく改革になりうると思われる。なぜならそれ(ジャーナリスト連合)は、『メディア企業(経営者)』と並ぶもう一つのメディアの自由(報道の自由)の主体を『あるもの』として顕在化させるからであり、同時に、その要素を欠いていることによってこれまでどうしてもうまくいかなかった政治権力・メディア企業・ジャーナリスト三者間の関係性を適正に構築する契機となるものでもあるからである。」(解説編、184頁)
ここで大石はポロリと、「これまで見てきた日本のメディアの諸問題の主病巣」と書いている。つまり事例とは「病巣」の事例という認識に立っていることを端なくも明かしてしまっている。ということは、大石は医者のように「報道のあり方にかかわる諸事例」を、あるいは「日本のメディアの諸問題」を観察してきたのである。それは臨床法学のアプローチの一つと言えるのではないだろうか? Clinical Professor of Low(臨床法学教授)である。彼は、日本のマスメディアの病巣を、病理を「客観的」に観察し、そのケースをできる限り多数収集して、その病理発生の形態の類型化を試みたのである。すなわち六つの類型とは、病理の発現形態あるいは発症のトポス(場所、現場)が六つに整理されたということだ。そして、その並べ方の順番にも意味がある。現象から原因へという流れになっている。
ということは、事例編とは「病巣」のコレクションであり、解説編とは「診断」の開示だと言えようか。では、「処方箋」はあるのか? それは何なのか? 上記の引用文の中から窺えるのは、大石は「ジャーナリスト養成教育制度」の導入と「ジャーナリスト連合」の結成が処方箋だと考えているということだ。その二つはともにジャーナリストの「専門性」、つまりプロフェッショナリズムにとっての核心的要素に他ならない。すなわち、「日本のメディアの諸問題の主病巣」の根っ子には「プロフェッショナリズムの欠如」という病因が横たわっている、したがってその治癒のためには患者にプロフェッショナリズムの思想の認識とそれに基づく選択と行動を促すことが必要だ、そういう論理になる。すなわち、患者自身が病いを治癒したいのであれば、体質改善が必要であり、生活習慣の見直しが必要だということだ。
少し補足すれば、事例のすべてがメディアの「病巣」とは限らない。特に「政治権力とマスメディア」「放送の公共性と独立性」の類型では権力の「病巣」や権力側とメディア側の癒着が「病巣」となった事例も多く収められている。
昔話を一つ
さて、私は本書が手元に届いて、それを目の前にした時、もう忘れかけていた昔のことを思い出した。私が東京大学社会情報研究所(現在の東京大学大学院情報学環)で仕事をしていた頃のことである。20世紀の世紀末、1999年頃のこと、私はそれまでの仕事、「公共圏」という概念の理論的精緻化・有効化という仕事から、その概念の社会的実践化・実用化という仕事へとシフトしていた。そのシフトを物語る言い方として、わかりやすく、そしてストラテジックに、「ジャーナリストは公共圏の耕作者(工作者)である」と表現していた。公共圏概念の社会的実践化・実用化のフィールドとしてジャーナリズムを選び、そこで公共圏概念の有用性を試そうとしたのである。別の言い方をすれば、一方から見てジャーナリズム研究に必要な理論的根拠として公共圏理論を据え、その適用能力を高めること、他方から見てジャーナリズム実践の再構築を通じて公共圏概念の有効性・正当性を証明すること、それらをしようとしたのである。すなわち理論と実践の架橋、あるいは両者の往還運動の実現を目指したのである。
もちろん「公共圏の耕作者」とはジャーナリストに限るものではない。建築家であってもいいし、デザイナーであってもいい。さまざまの分野で表現・創造活動に関わり、それを公開し、公共圏に働きかけ、「公共圏という社会空間」の中で交通・交渉関係に入っていく者たちである。公共圏を押し広げ、自由で活発な交通を実現しようとする者たちである。場合によれば、科学者や研究者もそこに入るだろう。しかし、すべてのジャーナリストが、すべての建築家が、あるいはその他の社会的工作者が「公共圏の耕作者」であるわけではない。そこには必要条件がある。
公共圏の耕作者たるべき者は個人であり、ミッションを自覚した行為主体として責任能力を持っていなければならない。そういう耕作者はどのようにして誕生するのか? 修行・修養を通じてであり、教育を通じてである。公共圏の耕作者としてのエトスとスキルが優れた実践者個人から可能性のある個人へと伝授され、その個人が伝授されたものをさらに磨きをかけてみずから血肉化しなければならない。その全体のプロセスが社会的な合意のもとに形成され、展開され、維持されていかなければならない。つまり耕作者教育の機会を個々の幸運に委ねるのではなく、その機会を誰にでも開かれたものとする社会的な制度化が必要だと考えたのである。
では、ジャーナリストの場合はどうか? 私は欧米のやり方を自分の目で確かめることにした。欧米の大学制度の中に設置されているジャーナリズムスクールやポインターインスティテュートのような独立した養成・研修機関の訪問を開始した。設置に至る歴史と考え方を調べた上で、現地でカリキュラムを見て、エデュケーターと話し、授業を参観させてもらった。私の最大の関心事はミッション設定と授業法(ディダクティック)が実際にどうなっているかだった。
そうした下調べと現地調査を経て、私は1999年に「諸外国におけるジャーナリスト教育の経験と日本の課題」という原稿を書き、同年『東京大学社会情報研究所紀要』第58号(創立50周年記念号)(121~152頁)に掲載した(花田達朗ジャーナリズムコレクション・第1巻・『ジャーナリズムの実践』彩流社、2018年の139~184頁に収録)。
問題は「日本の課題」である。日本において、この制度化は可能なのか? そこでふと考えた。必要性をただ唱えていただけでは、何も始まらないのではないか? それが日本でも可能であることを実証しなければ、社会全体がその可能性の現実化・実用化に向かっては動かないのではないか? 実用化試験の一定程度の成功があって初めて、社会的な導入への賛同と協力が得られるのではないか? イノベーションのプロセスとはそういうものだろう。
本書の前史
私はやがて試行実験に取り掛かることにした。つまり授業開発である。それは一人ではできない。目的に賛同される方々の協力が必要だ。私は人を募った。そのうちの一人がメディア法を専門とする大石泰彦だった。メディア倫理、あるいはジャーナリスト倫理の授業はカリキュラムに必要不可欠だ。私は大石に会って、プロジェクトの目的を話し、その授業を担当してくれないかと打診した。大石の返事は芳しくなかった。自分の仕事ではないし、そもそも倫理というものが教育の対象になり得るのかと、懐疑的だった。まったく乗り気ではない。「まずい。考えが甘かったかもしれない。」私は腹を括って、説得に取り掛かった。
その際、私はミッションとメソッドから大石に迫ったことを覚えている。メディアおよびジャーナリストの倫理を授業で取り扱う時のミッションについては、その時に咄嗟に考えた。キーワードは「制度の倫理」と「日常の倫理」、あるいは「大倫理」と「小倫理」だった。「大石さん、あなたはメディア法学者として憲法やメディア法の研究を専門にしてきて、そこからメディアの倫理についても言及してこられた。それは『制度の倫理』ないしは『大倫理』だと言えるのではないでしょうか? それとは別にジャーナリズムの行為者・実践者にとっての『日常の倫理』ないしは『小倫理」というものがあるのではないでしょうか? 法学者として『制度の倫理』と『日常の倫理』をブリッジすることは面白い仕事ではないですか?」
大石の目が少しだけ輝いた気がした。しかし、まだ浮かぬ顔をしている。面倒なことに巻き込まれたくないという気持ちなのかもしれない。何とか逃げ出そうとしているフシもある。私は話をメソッドに移した。「では、どうやって教育するのか、その方法論が問題ですよね。徒手空拳ではできません。単なる経験談や成功体験の話では教育になりませんからね。ディダクティックなメソッドが必要です。重要な方法はケーススタディーズだと思います。ケースを通じて、それを教材にして学生を教育するのです。」これは、その時に思い付いたことではない。
倫理を教育対象とするための方法論
欧米のスクールオブジャーナリズムを視察した時に気が付いたのは、ケースを収集し蓄積し、それを教育資源として活用するというやり方だった。例えば、米国の名門ミズーリー大学では見学している中で、Freedom of Information Center(情報の自由センター)という所にも案内された。そこでは、専任スタッフが情報自由法に関わるあらゆる事例(特に法が破られたり、破られた疑いのある事例)を収集していて、それを教育や研究に活用していると説明された。整然と林立するキャビネを目の前にして、ただ事ではない熱意と執念を感じた。なるほど、事例のデータベースは教育研究活動の、まさにインフラだと思った。英国のジャーナリズムスクールの名門はウェールズにあるカーディフ大学のスクールオブジャーナリズムであるが、そこを訪問してジャーナリスト出身の教員たちと研究室で話している時、私が「授業のメソッドは何ですか?」と聞いたら、彼は立ち上がってキャビネに行き、そこから何枚ものシートを取り出してきて、「ケースだよ」と言った。そのシートの1枚1枚が彼の収集したケースであり、授業で使うケースなのだった。その日の授業のテーマに沿って、キャビネからケースを引っ張り出して使うわけだ。ここでもケースが資源化されて、授業に活用されていた。目に焼き付いた、そうしたシーンが大石の説得の時に蘇ってきたのだ。
ジャーナリスト養成教育におけるジャーナリスト倫理の授業について、そのミッションとメソッドの説明を聞いた大石は、興味をそそられたという表情へと変わり、「ケーススタディーズというのはいいですね。やってみましょう」と言った。プロジェクトの重要な柱となる一人を獲得した。
東京大学での大石の授業が始まり、私も出席した。授業はどのようにイノベーションを遂げていくのか? それを観察しようと思った。そして、私が東京大学から早稲田大学に移ったことにより、2006年以降その授業は、早稲田大学で全学共通副専攻ジャーナリズムコースの基幹授業「ジャーナリズム概論」へと場所を移して継続された。フェーズは試行実験から実用化試験へと進んだ。そして、毎年度ごとに完成度を上げていき、遂に職人芸の域へと達した。ある時私は大石の授業が終わって、「この授業、本にできたらいいですよね?」と彼に言った。だが、難しいのは二人ともわかっていた。というのは、授業の要は配布資料で、A3サイズの用紙何枚にも渡って、事例となる各紙の新聞記事がびっしりとコピーされたものだった。それを大学の授業担当事務スタッフが事前にコピーして、教場に運び込んでくれていた。受講者数は当初の多い年で500人、少なくなった年で200人くらいだった。著作権法上、新聞記事のコピーを教育目的で授業で使用するのは許容されると解釈されていた。しかし、それを書籍化して販売することは新聞社が許さないだろう。そうなると、肝心な部分を欠いた出版物になってしまう。
今回出版された本でも、新聞記事のコピーは残念ながら含まれてはいない。しかし、あれば、極めて有用である。
思い出してみれば、その頃私は(おそらく大石もまた)、日本のメディア報道をジャーナリズムへと改良・改善していくことがまだ可能だと信じていたと思う。すでに手遅れかもしれないけれども、改革への可能性がまだ残っていると考えていたと思う。だから、いわば「最後の試み」としてジャーナリスト養成教育の制度化に賭けたのである。しかし、その淡い希望はその後の出来事によって見事に裏切られた。その楽観的な見通しは完膚なきまでに粉砕された。
焼け野原に立って風刺に快感を覚える
その出来事とは、2014年に発生した「朝日新聞『吉田調書』記事取消し事件」である。この出来事は日本のマスメディアおよび報道に対する、それまでの私のものの見方に根本的な変更を迫った。少なくとも私にとっては、考え方と態度の決定的な転換点となった。すべての幻想(イリュージョン)を捨てた。この大事件については、私はこれまで何度も書いてきた。したがって、ここでは繰り返さない。ただ、その事件の位置付けがいかに大きいかは、大石が「解説編」の冒頭でこの事件を取り上げていることからもわかろうというものである。この事件は、大石へは大石への大きなインパクトを、私へは私への大きなインパクトを与えた。
そうしたことを体験した後で、大石と私は再び一緒に仕事をすることになった。大石泰彦編著で『ジャーナリズムなき国の、ジャーナリズム論』(彩流社)を2020年に刊行したのである。そこで大石は講演の「『取材の自由』のない国で、いま起きていること」を文字化した、本全体への問題提起となる原稿を1本と、書き下ろしの「『ジャーナリストの自由』の不在が意味するもの」という原稿を書いている。
その講演は、大石が同書の「むすびにかえて」で書いているように、2018年5月に行われた。上記の朝日新聞の記事取消し事件から4年が経っていた。その年の3月に私は早稲田大学を定年退職していた。講演は、「大学発メディア」だったワセダクロニクル主催で行われた、「世界プレスの自由デー」記念イベントの基調講演として行われ、会場は大学の教室などではなく、街中のレンタルスペースだった。マンションの一室のような作りだった。そこに読者や寄付者が集まって来た。主催者の控え目な予想を超えて、徐々に室内の椅子はほぼ埋まってしまい、開始直前にも到着する参加者が絶えず、講演者であり、主役たる大石はとうとうキッチンスペースへと追いやられ、キッチンのシンクの前に立ってカウンター越しにギッシリ詰まった30名ほどの聴衆に向かって第一声をあげるハメとなった。参加者は主催者が提供したピザを頬張りながら彼の話を聴いた。
この異様な状況が功を奏して(?)、大石の語り口は冴え、会場は熱を帯びた。実に、ユニークな、祝祭的な空間と時間になったのである。その稀有な語りと内容をここで再現することはできない。本に記録され刊行され残されているので、ぜひそれをご覧いただきたい。ただ、私がそれをどういう語り口だと観察したかというと、それは諧謔とか風刺とかの趣があり、同時に箇所によっては自嘲的な雰囲気もあり、こう言うと大石には悪いが、ちょっとしたエンターテインメントであった。私は大石の「ギャグ」を楽しんだ。ピザが口から飛び出して、向かいに座る人の顔にまきちらされてはいけないと、私は爆笑を懸命に堪えた。
しかし、そのスタイルはその内容の辛辣さを直接的に提出することを回避するための戦術であり、辛辣さを陰に隠すための一策であったことは私の目には明らかであった。大石は「ここ数年の間、この国の状況を観察しつつ温めていた考えを思い切って喋ってやろう」(同書、223頁)と臨んでいた。そういう時、おそらく大石には「大上段に」「偉そうに」「カッコよく」話すこと、批判することは自分にとっては恥ずかしいことだというモラルというか、美学があるように思われる。だから、辛辣な内容をエンタメにして喋った、いや、そうせざるを得なかったのだ。私が間違っているかもしれないけれども、私にはそう思われた。それは痛烈な批判だった。
その講演で大石は、いわば「身も蓋もないこと」をあからさまに喋っているのである。わかっている人でも「見ないふり、知らないふり」をして決して喋らないことを臆面もなく棚ざらしにしているのである。それはタブーの暴露とはちょっと趣が違う。大石が喋ってしまったことはタブーではない。村社会の掟でそれを公にすることが強く禁止されているようなこと、禁制ではない。意識さえすれば、観察しようとしさえすれば、誰の目にでも見えることである。ただ、目のレンズの焦点を合わせる意思がなければ、何も見えないだけなのだ。業界の人々のみならず社会の人々もこれを見ようとしなかったのは、いわば集団的催眠状態にあったからだと言えよう。
その催眠術に抵抗して覚醒を促す手段として、諧謔や風刺は有効であろうと思われる。状況について絶望感に苛まれた者は、この手法を追求することで、暗い深淵に引き摺り込まれることなく、自分の身を軽くすることができるかもしれない。「笑い」で自分が救済されるかもしれない。同時に、オーディエンスとして一緒に笑う人々はその「笑い」で固定観念の縛りを解いて自由になることもできる。こうして、その場所に「笑い」の解放感という共同性の成立を見ることができるだろう。大石にはあの講演の路線をさらに続けて発展させてほしい。もしも私が出版社の編集者で、あの本を読んだとしたら、そのチャンスを見逃さないだろう。大石に新書の書き下ろしを提案するだろう。仮題は『笑ってジャーナリズム考』。
風刺は、ジョナサン・スウィフトの『ガリヴァー旅行記』がそうであるように、ジャーナリズム精神の実践である。来るべき大石の新書の本題は原稿の出来上がりを見てから編集者が考えても良いが、『オオイシのジパング・メディア観察奇譚』というのもいいかもしれない。風刺とは、日本メディアを席巻する吉本興業の「お笑い芸人」の「お笑い」とは違い、権力に抵抗する創作活動である。ジャーナリズムの一形態としての風刺は、この国でもっと研究対象にされて良いし、表現活動のジャンルとしてもっと活発になることが望まれる。
本当はないのに、まるであるかのように
大石はその講演でも、大学での授業の時のように事例を通じて説明し、事例として新聞記事のコピーを使った。講演の表題にあるように、メディア企業は、本当は「取材の自由」はないのに「まるであるかのように」振る舞い、その便利な言葉を「一つの『商標』」(同書、41頁)として用い、「体制の中の、ある種のほど良い『うるさ方』の役割」(24頁)、つまり「免震装置」(24頁)の役割を果たし、「あまり大きな声では言えないが、公務として統治機構の枠内でその業務を遂行している」(34頁)と、喝破している。これが「『日本型ジャーナリズム』という異形のシステム」(49頁)の実相なのである。そのシステムは、「ジャーナリズムではない、何ものか」なのだ。
そして、その「公務」こそが、依然としてこの国の多くの法学者や裁判官が、またメディア業界人や一般人の大部分が肌感覚で理解している「メディアの公共性」だと言える。それは日本特有の「公共性」の理解であって、私の「公共性」の理解からすれば真逆である。日本における「公共性」概念の意味転換をはかろうとした、私の公共圏論は多勢に無勢だった。人々の認識と状況が変わることはなかった。
大石の言う「日本型ジャーナリズム」とは、戦後このかた自称でも他称でも一般に「マスコミ」と呼ばれてきた。「本当はないのに、まるであるかのように」という問題提起を受けて、その本の中で私は、「日本『マスコミ』はジャーナリズムではない─その虚構と擬制の構造分析」という表題の原稿を書いた。私も「思い切って」書いた。しかし、残念ながら、そこには「笑い」はない。その原稿をもって私は日本「マスコミ」に批判的に関与することから決別し、「お別れです」と告げた。もう何も可能性を見ないし、もう何も関わらないし、したがってもう論述する関心対象とはしないという結論を出した。私はジャーナリズムを偽装する日本「マスコミ」にはいかなる改革の可能性もないという結論に達したのである。
日本「マスコミ」をジャーナリズムたらしめんとする改革提案、すなわちジャーナリスト養成教育制度の導入、個人加盟のジャーナリストユニオンの結成、プレスカウンシルの設置、主権回復後に吉田茂内閣によって廃止された電波監理委員会の再導入、それらのどれも夢のまた夢だった。そのうち私自身が東京大学と早稲田大学という場所で試みたジャーナリスト養成教育の制度化の開始は失敗に終わった。大学の中にもメディア業界の中にも日本社会に中にも共鳴板はほとんどなかったと言ってよい。そのことを予見できなかったわけではないが、有効性・有用性の実証を成功させることによってその「存在しない」共鳴板を作ってやろうという思いの方が優位に立っていた。むしろ感度の良い共鳴板を持っていたのは一部の学生たちだった。他の改革提案の場合でも、日本のマスメディアの中にそれらを目指す、どのような当事者意識も立ち上がらなかった。過去もそうだったが、今日でも、どこにも煙は立たず、芽も出ず、無風の状態が続いている。現場からは、産みの苦しみを引き受けるようなリーダーも運動も現れなかった。今見られるのは、空洞化した日本のマスメディアの土俵の外側で、新しいジャーナリズムを創り出そうという産みの苦しみ、いや創造の楽しみである。そこでは確実にマスメディアの20世紀が終わり、着実にインターネットの21世紀が進んでいる。
本書の存在意義
さて、こうした経緯を経て、大石も私も2025年の日本の中にいる。21世紀もまさに四半世紀が過ぎた。そして、大石は『メディア報道の四半世紀』を上梓したわけである。大石にとっての、この出版の意味とは何なのだろうか?
「解説編」の「おわりに」で、大石は次のように書いている。「変な言い方かもしれないが、この本の『内容』ではなく、この本の『存在』そのものが、日本のメディア研究に対して私が『本当に言いたかったこと』であるような気がしているのである。これはかなり意味不明瞭で補足説明を要すると思われる感懐ではあるが、願わくは本書、そして本書のメッセージが、私個人にとって重要であるだけではなく、日本のメディア研究において多少の存在意義を持つものであってほしい。」(解説編、192頁)
大石は、この本の「存在」の意義を日本のメディア研究において求めている。ジャーナリスト養成教育にはもはや求めていないし、それについて言及することもない。仮に本の「内容」が同じようなデザインだったとしても、つまり事例と解説という内容であったとしても、今その本が「存在」する時代のコンテストはかつてとは違う。置かれた文脈が変化して異なっていれば、本の意味や意義、そして役割は必然的に異なってくる。
地道な努力が傾けられた末、本書が遂に完成した時、マスメディアを前提としたジャーナリスト養成教育の可能性を追い求める文脈や環境はもはや存在しなかった。それでも、研究者としての大石は、本書の完成で、「これまでの研究生活では感じたことのなかった大きな充実感のようなものを覚えている」(解説編、192頁)と率直に述べている。「自己懐疑でなく充実感、それはめでたい。良かったですね」と、私はかってプロジェクトを共にしてくれた大石に心からの労いの言葉を贈りたい。
最後に
では、私にはこの本はどのように見えるか? 大石の言う「日本型ジャーナリズム」、私の指す日本「マスコミ」は、この四半世紀をかけて緩慢なる死を辿ってきた。権力に殺されるのでなく、毎日毎日少しずつ自分を殺してきた。「忖度死」と言っても良い。自分で自分の首を絞めては衰弱し、自分で墓穴を掘ってきた。無自覚的に、無意識に、無目的に、ただ自壊している。自滅している。日本「マスコミ」自体、生きたいという願望や欲望は持っていないように見受けられる。本書に収録された事例は、墓標である。事例751を数える「事例編」が作り出す風景は、私の視界の中では墓標の林立として広がっている。
(ホームへ戻る)