人生の第4四半期
また誕生日がやってきて、今日、8月27日で78歳になった。
70歳代になって気が付いたことがある。それは、わが人生は25年単位で動いてきたし、これからもそうだろうということだ。つまり、100年の四半期ごとに区切りを付けて進んでいるということである。その流れは、『花田達朗ジャーナリズムコレクション』 全6巻(彩流社)に付した年譜からも確認することができる。
27歳で日本を脱して外国へ出て、当時の西ドイツに着地した。大きな転身だった。28歳の誕生日は1975年にミュンヘン郊外のシュタルンベルク湖畔の村ベルクで迎えた。その時、第1四半期は終わり、第2四半期へと入ったわけである。その第2四半期の半分近く、11年間の歳月をその異郷で送った。そのあとで、新しい異郷としての日本に入境して、残りのほぼ半分を過ごした。なぜそこが異郷かと言えば、その間もドイツの時間意識と言語の反映の中で生きていて、ドイツ語で考えて、日本語で書いていたからである。
28歳から52歳の終わりまでが第2四半期だったが、では、その終わりに何があり、どういう区切りが付けられたのか? 52歳の誕生日は1999年に東京で迎えた。誕生日の前後のことを年譜で確認してみると、三つの出来事が目につく。第1は、その年の7月に「諸外国におけるジャーナリスト教育の経験と日本の課題」という、かなり長い原稿を脱稿している。そのテーマについて初めて書いたもので、端緒であり、同時に結論でもあった。これは同年中に、『東京大学社会情報研究所紀要』第58号(創立50周年記念号)に掲載された。第2は、8月にユルゲン・ハーバーマスをシュタルンベルクの自宅に訪ねている。それは最初の自宅訪問だった。この時は、書斎で3時間ほど話をした。第3は、11月に『メディアと公共圏のポリティクス』(東京大学出版会)を刊行している。最初の単著『公共圏という名の社会空間』(木鐸社、1996年)の刊行以降の3年間に書いた論文を収録したものだった。
以上の三つは相互に絡まり合っていて、ほぼ同時に起きた。どう絡まっているかというと、単純に言えば、それまでやってきた公共圏論の仕事に決着を付けて、シャーナリズム論・ジャーナリスト養成論の方へと方向転換したということになる。そういうターンをこの年に切ったのである。
補足すれば、その夏帰国してから、その本の出版作業で少し残っていた校正をやり、「あとがき」を書いた。その冒頭にシュタルンベルク訪問の印象記を置いた。そして、その本の刊行とともに私にとっての公共圏論の季節は終わったと感じた。少なくとも私としてはもうすべて書いてしまった、書くべき新しいアイディアはもう出てこないだろうと予感したのである。だが、次にどんな新しいものの見方があるのかは、まったくわからなかった。ただ、ジャーナリズム現象を対象化した仕事をしていった中において、その裏で公共圏論とカルチュラル・スタディーズが人に知らせることなく密かにバックボーンとなっていたのは確かだ。つまり、新しい認識枠組みはまだ見出してはいなかった。

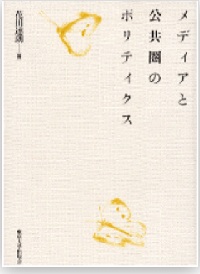
次の第3四半期は53歳から始まり、77歳で終わった。2000年から2024年までの25年間である。その間に70歳の誕生日を2017年に迎え、2018年3月に大学を定年退職した。しかし、退職は大きな転換とはならなかった。先に挙げた著作集 全6巻をまとめる仕事が入り、意識の連続性の中に置かれてしまったからである。刊行は予想外に長びき、完結したのは2022年4月のことで、そこで過去からの連続性から解放された。その時、まだ74歳。そこからジワジワと転換のための準備段階が始まった。77歳が終わるまでに2年とちょっとを残していた。不思議なことに、頭の中の組み立て、意識の持ち方、身体の感覚などが1ミリづつ変化し始めた。
そうした中で、2024年4月に「第三のジャーナリズム」の原稿を一気に書き、それは創刊された総合雑誌『地平』の7月号から短期連載として掲載された。また、Tansa編集長の渡辺周さんと一緒に原稿を書いてきた『自由への逃走−ナオはジャーナリズムに出会っていい子でいるだけの毎日をやめた』(旬報社)が2025年4月末に完成し、見本を手にした。5月に書店に並んだ。両方の著作とも私の過去の著作とは訣別していると言ってよい。方向転換はすでに行われた。
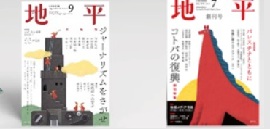
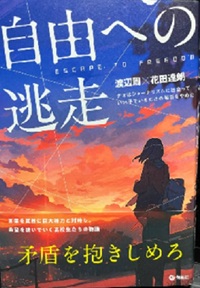
ちょうどその頃である。かけいをつたって流れ来る水で満杯になり、鹿おどしの竹筒が回転し、石を打ってカーンと音を響かせるように、流れ来る意識と無意識が臨界点に達したかのごとく、私の頭に東京を去って群馬県前橋市へ移住するというアイディアが立ち上がった。それは、新宿御苑のプラタナス並木の下のベンチに座って、空を眺めていた時に起こった。清々しい経験だった。そして、私はすぐにアクションを起こした。縁もゆかりもない土地、誰一人知り合いのいない前橋市に5月3日の憲法記念日に電車で向かい、その駅に降り立ち、街を歩き回った。街の落ち着きと、山並みの見える風景、そしてそこに吹く風を大いに気に入った。翌日から不動産屋を通して住居探しに取り掛かり、幸運なことに、それはあっという間に成果が出た。
こうして私は6月20日に前橋に引っ越し、短期移住プロジェクトは首尾よく完了したのであった。77歳が終わるまでに何かが起こるだろうという私の予感は、こういう形で実現した。そして、今日、私は78歳の誕生日を前橋で迎えた。こうしてわが人生の第4四半期が始まったのである。その期間は、プログラム上(理論上)、78歳から102歳までが想定されている。その内容がどのようなものなるか、それは今、私の意識と無意識とが感じ取り、予測し、そして計画していることだろう。
なお、全体としては、四半期の25年間というサイクルは維持されているものの(27歳まで、28歳から52歳まで、53歳から77歳までのそれぞれ25年間)、2年間ズレているのはなぜか? 私の推測は次の通りだ。私は満1歳の時に小児麻痺(ポリオ)に罹り、高熱を発し、生死を彷徨った。そして、かろうじて生の側に回収された。だが、この虚弱な命をそのまま生かすか、断念するかはまだ様子眺めで、天が最終決定を下したのは私が2歳の時だった。私はそのまま生きて良いことになった。つまり、私は3歳から改めてこの生を生き始めたのである。ゼロ期が終わってそこから第1四半期が始まった。スタート時点での事情が響いて、数字に2年間のズレが常に生じているのである。
人生の第4四半期、どういう展開になるか、ワクワクしている。しがらみの無い、この旅はスリル満点!
ホームへ戻る

群馬県庁32階から見下ろす利根川