�����{��`�����̍������Ƃ̂������@�ȉ����c�搶�̃u���O���
���Љ�������܂������c�ł������܂��B�����A�����̂Ƃ���A�M���يْ��Ƃ����N���m��Ȃ��悤�ȔC�Ӓc�̖̂��O�̒��𖼏���Ă���܂��̂ŁA����Ȃ�����Ƃ����w�p�I�ȏW�܂�ɌĂ��ƁA�������܂�Ȃ��C�����ɂȂ�܂��B
���́A��{�I�ɑS�Ă̖��Ɋւ��đf�l�ł������܂��āA�ł�����A���܂��̂���ׂ邱�Ƃɂ͌��������Ȃ��Ƃ��A�G�r�f���X���Ȃ��Ƃ������Ă��A����͂�������Ƃ��������悤������܂���B�����A�f�l�ɂ͑f�l�̋��݂�����܂��āA���������Ă��w���I�ȁA�w������I�ȃo�b�V���O���邱�Ƃ͂Ȃ��A�����猾�������đf�l�Ȃ��炢������Ȃ����őS���ς܂�����B
��w�̋��t�Ƃ����̂͌듚�������X��������܂��āA�啗�C�~���L���邱�Ƃɂ��Ă͋����}���������B���͂��̓_�ŗ}���̂Ȃ��l�Ԃł������܂��āA�ق�Ƃ��͎��̂悤�Ȗ���}�Ȑl�Ԃ��������������ق����A���̒��A���ʂ����悭�Ȃ��Ă悢�Ǝv����ł��B
����ɈӊO�Ȃ��ƂɁA���̑f�l�̒���������Ȃ��B
�v���o���Ă������Ȃ��Ƃ������ł�����ǂ��A����������\�N�߂��O�ł��傤���A�����w�X��̒����_�x�Ƃ����{���o������Ɍ����������̐l���q�˂Ă܂���܂����B�u�����������ł��v�ƌ����Ė��h���o���āA�u���Ȃ��̃t�@���Ȃ�ł��v�ƌ�����ł��B�������������t�@���̂킯���Ȃ��B�i�j
���낢��Ƙb�����Ă�����A�u���Ȃ��̒����_�Ȃ�ł�����ǂ��A���̒����̋��Y�}�����̏������Ȃ��͂ǂ�����Ď�ɓ����ꂽ�̂��v�Ɛu���Ă����B�u�����V������ł��v�Ƃ�����������A���������Ă��炵���B�u�����āA�V���ŏ����Ă����������āA�f�Ђ��Ȃ����킹�Ă����Ƒ�̉����N���Ă��邭�炢�͑z�������܂��ł���v�Ɛ\���グ����A�Ȃ��Ȃ��ЂÂ��Ȃ���ł��A��ɂȂ�܂����B
��ʂ��A������Ǝ����b�ɂȂ�܂����A�������Y�}�ɒ����I���ψ���Ƃ������̂�����܂��āA�������}�����ɐ��E�}�����w�����܂����B�}�������ǂނׂ��{���\�Z�������āA�����ǂ�ł����悤�ɂƁA�ċx�݂̉ۑ�}���݂����ɋ��������X�g�̒��Ɏ��́w���{�Ӌ��_�x�������Ă���܂����B���{�l�����������͖̂l�̖{���������������ł��B�����l�̗F�B���畷���܂����B�u���c����A���Ȃ��̖{�A�o�Ă���B�I���ψ����͏K�ߕ�������A�K�ߕ����F�߂��{����I�v�ƌ����܂����B�������������Șb���Ǝv����ł�����ǁA���{�̃��f�B�A�͂��܂���Ă���Ȃ������ł��ˁB
���Ƃقǂ��悤�ɑf�l�̒����͕���Ȃ��Ƃ������ƂŁA�{���͎��{��`�����̍������Ƃ̍s���ɂ��Ĉ�Ȃ��b�������Ē����܂��B
����Ȃ��Ƃ�����ׂ鎑�i���N�ɂ���̂��Ƃ����悤�ȑ�Ԃ�̉���ł�����ǂ��A�B�X���邻���������鐭���w�҂̐搶�����̑O�ł���ׂ点�Ē����܂��B�搶���͂�͂�w��I�������Ƃ������Ƃ��d���闧��ɂ���܂�����A�y�X�Ȃ��Ƃ͌����Ȃ��Ǝv����ł�����ǂ��A���͑f�l�ł�����A���������C�Â������v��Ȃ��B�����͌���ꂽ���Ԃł͂���܂�����ǂ��A����Ȃ��Ƃ������ċA���Ă��������Ǝv���܂��B���Ɋ��҂���Ă���̂��A�����������Ƃ��Ǝv����ł��B�Ƃ肠�������C�~�����L���Ă����Ă��������A���͂����炠���Ă��\���܂���Ƃ����̂��u���˗��̎�|���Ǝv���܂��B
����ɁA�����A���͎����ڂ��Ȃ�ł���ˁB����̖�A���[�}����A���Ă����Ƃ���ŁA���ꂩ�玞���ڂ���D���ɂȂ��Ă���Ƃ���Ȃ̂ŁA�オ���܂����Ȃ���ł��B���A�ӂ���A��������Ƃ�����ł�����ǂ��A�����͂����̎������炢�̃e���V�����Ȃ̂ŁA���g���������炢�̃N�I���e�B�[�ɂȂ�\��������܂��̂ŁA���̓_�����e�͂��������B
�܂��A�����̃e�[�}�ł����A���{�����A�Ȃ����̂悤�Ȑ��������݂��Ă��āA�N���x�����Ă���̂��B�����{�̖����`�Љ��Ȃ����̂悤�Ȑ��̂����ݏo����A����ɑ��Đ��������f�B�A������Ȃ�̎x����^���Ă���̂��Ƃ����A���ɂ킩��ɂ����������ǂ��Ă݂����Ǝv���܂��B
�������̂���悤�𐧓x�̗A���x�̕���Ƃ����悤�ɁA��قǎR���搶���������Ⴂ�܂�������ǂ��A��������鑤�ɂ���ϓI�ɂ͍�����������킯�ł��B���������Ƃ����Ă���A�������Ƃ����Ă���A���{�̍����̂��߂ɂ���Ă���ƁA�{�l�����͂�����������ł���킯�ł��B���߂�����{������Ă�낤�Ƃ����悤���S�������Ă���Ă���킯����Ȃ��B��X�̑����猩��ƁA���{�̐��x���Ԃ����킵�ɂ��Ă���悤�ɂ��������Ȃ���ł�����ǂ��A����ɂ͎�ϓI�ȍ�����������B��ϓI�ɂ͎����ѐ�������B���Ԃ������Ƃ����Ă������ł���B�l�Ƃ��ẮA�����̔��f�������������ɓ���āA�ނ�̑��̎�ϓI�Ȏ����ѐ��������Ƃ������Ƃ����Ă䂫�����ƍl���Ă��܂��B
���ɊC�O���猩���ꍇ�ɔ��ɂ킩��ɂ����Ǝv���܂����A���{�̍��Ɛ헪������т��āu�Εď]����ʂ��Ă̑ΕĎ����v�Ƃ������̂ł��B���ꂪ�����{�̊�{�I�ȍ��Ɛ헪�ł��B
�ł��A���́u�Εď]����ʂ��Ă̑ΕĎ����v�Ƃ������Ƃ͓��{�l�ɂ͂킩�邯��ǁA��������͂��̗��H�������ɂ����B
�l�́A�l�I�ɏ���ɂ�����u�̂���헪�v�ƌĂ�ł��܂��B
���{�l�̏ꍇ�A�̂���Ƃ����̂́A���Ƃ킩��₷���L�����A�p�X�ł��B���t�ŕ���ɏオ���āA���ɂȂ��āA�ԓ��ɂȂ��āA��ԓ��ɂȂ��āA������A��U�߂���Ă�āA�u���܂����������Ƃ悭���`��s�����Ă��ꂽ�ˁB���ꂩ��͈�{�������Ă�낵���B�����̂̂����Ă�邩��A���ꂩ��͎����̍��z�ł��Ȃ����v�ƁA�����ۂ�Ƃ�������āA�Ɨ���F�߂��āA�����̓X�̎�ɂȂ�B���������悤�ȃL�����A�p�X�Ƃ������A�v�����[�V�����E�V�X�e���Ƃ����͓̂��{�Љ�ɂ͓`���I�ɑ��݂��Ă��܂����B
�@������A���{�l�ɂƂ��ẮA�u�O��I�ɒ��`��s�����A�O��I�ɏ]�����邱�Ƃɂ���āA������A�V���̂��Ƃ������̓����J����v�Ƃ����\�}�ɂ͏�������a�����Ȃ��Ǝv����ł��B�����{�l���u�Εď]����ʂ��Ă̑ΕĎ����v�Ƃ������Ɛ헪�ɔ�r�I�ȒP�ɔ�т����̂́A�����āA���̂��Ƃ́u�ُ킳�v�ɂ��܂��ɋC�����Ȃ��ł��邱�Ƃ̈�̗��R�͂��́u�̂���헪�v�Ƃ������̂����{�l�̎Љ�ӎ��̒��ɂ��Ȃ�[���������낵�Ă�������ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���̓`�������ł��B
�Εď]����ʂ��Ă̑ΕĎ����Ƃ����̂́A�s�풼��̐�̊����{�ɂ����ẮA����Ȃ�ɍ����I�ȑI���������Ǝv���܂��B�Ƃ�����肻��ȊO�ɑI�������Ȃ������B�R���I�Ɍ���I�Ȕs�k���i���āA�f�g�p�̎w�߂ɏ]�������Ȃ������킯�ł�����B
���̏�Ԃ���A���J�I�Ȕ��̏�Ԃ���E�p���邽�߂ɂ́A�Ƃ肠�������̍��ɂ͂����A�����J�ɑ��Ē�R����悤�Ȑ��͂͑��݂��Ȃ��A���W�X�^���X���Ȃ����A�p���`�U�����Ȃ����A�\�A�⒆���̍��ۋ��Y��`�̉^���ƘA�����鐨�͂��Ȃ��Ƃ������Ƃ������i����K�v���������B��X�́A���̂��ƌR���I�Ȓ��ړI��̑̐�����E�����Ƃ��Ă��A�����ăA�����J�ɔ���������A�A�����J�ɑR����G�ΐ��͂Ɠ��������肷�邱�Ƃ͂���܂���Ƃ���������Ȃ��A�m��^���Ȃ��ƁA�匠���ł��Ȃ������B���������؉H�l�܂�������������킯�ł��B
���̎����ɂ����āA���ۂɂ͖ʏ]���w�ł������킯�ł�����ǂ��A�Εď]���Ƃ����헪��I���Ƃ́A�q�ϓI�ɂ���ϓI�������I�ȑI���������Ǝv���܂��B����ȊO�̑I�����͎�������{�ɂ͂Ȃ������B
�ł�����A�g�c�A�ݐM��A�����h�삠����܂ŁA��㎵�Z�N��Ȃ��܂ł̐�㐭���Ƃ����́A�Εď]����ʂ��ăA�����J�̐M�����l�����āA����ɂ���ăA�����J�ɒ��ړ�������Ă��鑮����Ԃ���A����Ƀt���[�n���h�����āA�ŏI�I�ɕČR��n�����ׂēP�����ꂽ��A���@�����肵�Ď匠���ƂƂ��Ă̖̑ʂ�����A�����������[�h�}�b�v��`���Ă����̂��Ǝv���܂��B�A�����J����u�̂���v���Ă��������A�O���ɂ��Ă��A���h�ɂ��Ă����{�Ǝ��̐헪��W�J���Ă䂭�B�����I���炢�����Ă��킶��ƓƗ������Ă����A���������C���ȃX�P�W���[����g��ł����낤�Ǝv���܂��B
���̃X�P�W���[���̑I���Ƃ����̂́A�����̓��{�ɂ����Ă͕K���̂��̂ł��������A�\���ȍ��������������Ǝv���܂��B�����āA���̐헪�̍��������m�M�������̂́A�����������̌�������������ł��B�Εď]��������A���܂��������B���̐����̌����������B
��́A���܈�N�A�T���t�����V�X�R�u�a���ł��B���Z�N�ڂɂ��āA���{�͌`�̏�ł͓Ɨ�������킯�ł�����ǂ��A�����̍��ێЉ�̏펯�ɏƂ炵�Ă��A����قǔs�퍑�ɑ��Ċ��e�ŗZ�a�I�ȍu�a���Ƃ����̂͗��j��Ȃ��Ȃ������o���������ƌ���ꂽ�قǂɁA����ȍu�a����ꂽ�B
����́A��͂肻��܂ł̂U�N�Ԃ̓��{�̑Εď]���̉ʎ��Ƃ݂Ȃ��ׂ��ł��傤�B�ł�����A���{�̈א��҂����́u�Εď]���헪�͐����������v�Ɗm�M���邱�ƂɂȂ����B�Εď]���ɂ���Ď匠�̉Ƃ����傫�ȍ��v���l�������B�������������̌��Ƃ��āA�T���t�����V�X�R�u�a���͋L�����ꂽ�̂��낤�Ǝv���܂��B
��������ł������A���ꂾ���傫�ȏ������A�����J���瓾��ꂽ�Ƃ������Ƃ́A���ꂩ�炳��ɑΕď]���𑱂��Ă��������قǁA���{�̎匠�̉͐i��ł䂭�Ƃ����y�ϓI�Ȍ��ʂ������̂Ƃ����{�l�����͐[�����ݍ��B
���܂肱���������Ƃ������l�͂��܂��A�Εď]���H���̓�x�ڂ̐����̌��͎���N�̉���Ԋ҂ł��B�����h��̓A�����J�̃x�g�i���푈�ɑ��đS�ʓI�Ȍ���x���̐����Ƃ�܂����B���ێЉ��̓A�����J�̒鍑��`�I�Ȑ��E�헪�ɖ��ᔻ�ɏ]��������{�̑ԓx�͂��т����܂Ȃ����ɔ�����܂����B�l���g���w���ł�������A�Ȃ������h��͂��̂悤�Ȗ��炩�ɋ`�̂Ȃ��푈�ɂ��Ă܂őΕď]������̂��A�{����ւ����Ȃ������킯�ł��B�ł��A�C�m�Z���g�Ȋw���̖ڂ��猩��ƔƍߓI�ȑΕď]���ł��鍲���h��̂ӂ�܂����A�����I�ȍ��v�Ƃ����_�Ō���ƁA����Ȃ�̍��������������킯�ł��B�`�̂Ȃ��푈�ɉ��S�����㏞�Ƃ��āA���{�͉���Ԋ҂Ƃ����O��I�ʎ����l���ł�����ł�����B�@
���̓�̐����̌������{�l�́u�Εď]���H���v�ւ̊m�M������Â����̂��Ɩl�͎v���܂��B���Ȃ��Ƃ���㎵��N�A����\���N�܂ł́u�Εď]����ʂ��Ă̑ΕĎ����v�Ƃ����헪�͊G�ɕ`�����݂ł͂Ȃ��āA���̌������������Ă����B����ǂ��A���̌��������������ɊɂȂ��Ă䂭�B
�l�Ԃ͈�x�L���������헪�ɌŒ�����X��������܂��B
�u�҂��ڂ����v�Ƃ������w������܂��ˁB���l�^�͊ؔ�q�́u�犔�ғe�v�Ƃ�����b�ł��B���̋��̐芔�ɂ��܂��ܓe���Ԃ����Ď�̍���܂��Ď��B�e�������A�����_�v�͂���ɖ������߁A���̓�����͍k����~�߂ďI���e�̗���̂�҂��������B���ɓe�͓�x�Ɛ芔�ɂԂ��炸�A���͍r��ʂĂāA�_�v�͍����̏����̂ɂȂ����B
�u�����͑听��W����v�ƌ����܂�����ǂ��A���{�͂��̔_�v�Ɏ��Ă���B���̓�̐����̌��ɂ���āA���̐����̌��A���̐헪�ɋ������Ă��܂����B���͂���������~���A������L���ɂ��A���ێЉ�ɂ�����M�F�����߂āA�Ɨ����A�匠���ƂƂ��č��ێЉ�ɏ��F�����Ƃ����I���ȓ�������A�����Εď]�����Ă���������悢�Ƃ����u�ғe�v�헪�ɐ�ւ����B
����܂ł̐�㐭���Ƃ����́A���Ȃ蕡�G�ȃ}�k�[�o�[����g���ē��ĊW���R���g���[�����Ă����Ǝv����ł��B�����Ƃ���łȂ��A�������w�҂�m���l���A���ĊW�Ƃ����͔̂��ɕ��G�ȃQ�[�����Ƃ������Ƃ��킩���Ă����B������I�݂ɃR���g���[�����āA�ł��邾���]���x�����炵�āA�ł��邾���匠�I�ɂӂ�܂��Ƃ����p���[�Q�[���̂��߂ɂ���Ȃ�̒m�b���i���Ă����B�Ȃɂ���A�A�����J�͓��{�ɂƂ��Ē��߂̐푈�̓G���ł�����A���܂��܂ȓ_�ō��v���Η����Ă���B��������āA�A�����J�̍��v������x�����A���{�̍��v�傳����Ƃ����g���b�L�[�ȃQ�[���ł�����A���Ȃ�̒m�I�ْ����v�����ꂽ�B
�Ƃ��낪�A�l�̈�ۂł́A���Z�N�ォ���A���������ْ����������Ƃ����Ɍ����Ȃ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B���ė������A���ꂼ��̍��v�������āA���Ɍ��������ʉ��̃o�g����W�J���Ă���Ƃ����������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�����P���ɑΕď]�����Ă�������������Ƃ�����Ƃ����v�����݂ɓ��{�̃G�X�^�u���b�V�������g�S�̂��̂����悤�ɂȂ����B�Εď]��������ƁA�u�������Ɓv������Ƃ����A�V���v���ȓ��͏o�͑��փV�X�e���A������u�y�j�[���K���E���J�j�Y���v�̂悤�Ȃ��̂Ƃ��ē��ĊW���\�z����l�������������ɑ����Ă��āA�C�����Α����h���`������悤�ɂȂ����B���ĊW�����́u�u���b�N�{�b�N�X�v�ɂȂ��Ă��܂��āA�u�Εď]���v�Ƃ����u�y�j�[���݁v����荞�ނƁA�u�Ȃɂ��������Ɓv�Ƃ����u�K���v���o�Ă���Ƃ����P���ȃ��J�j�Y�����z���蒅���Ă��܂����B����Ȃӂ��ɓ��ĊW����������V�����āA���z�̗̈�ɕ����オ���Ă��܂����̂��A���������W�O�N��Ȃ������ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�ǂ����Ă���Ȃ��ƂɂȂ����̂��Ƃ����ƁA���ǂ́u���Ԃ̖��v�������Ǝv���܂��B
�u�Εď]����ʂ��Ă̑ΕĎ����v�Ƃ������z���̂��̂̍������́A�m���ɘ_����܂ł��Ȃ��B�ł��A���Ԃ������Ă���ƁA���̑��u���Ǘ��^�c����l�Ԃ�����ւ��B�s�풼��̂Ƃ��A���{�̊O��헪�̃t�����g���C���ɂ����l�����́A���Ă̍��v�̊Ԃɂ��ꗂ�����B�����̍��v����v����Ƃ������Ƃ͌����I�ɂ͂��肦�Ȃ��Ƃ������Ƃ����g�ɂ��݂Ēm���Ă����B������O�ł��A�E�����������Ă�������Ȃ�ł�����B���v����������Ƃ������Ƃ��킩������ŁA�u�ʏ]���w�v�̃}�k�[�o�[��W�J���Ă����B�\�ʓI�ɂ̓A�����J�ɒǐ����邪�A�{�S�ł͑����A�����J������������Ǝv���Ă����B
�ł��A�ʏ]���w�̃|�[�Y�����ꂪ��O����ɂ킽���đ��������ɕώ����Ă��܂��B�u�ʏ]�v�������c���āA�u���w�v�������Ă��܂��B�Εď]�������̂܂ܓ��{�̍��v����ł���Ɠ�����M�����ސl�����������Ă����B�����Ă����ǂ���ł͂Ȃ��A���E�A���E�A���f�B�A�A�w��A�ǂ��ł��A�Εď]���E���ē����@���ȊO�̑I�������l�������Ƃ�����l�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B
�ȑO�A����A�����J�����̐��ƂɁu���ē����ȊO�̈��S�ۏ�̑I�����v�ɂ��Ď��₵�����Ƃ�����܂������A����ɋ����Đ�債�Ă��܂��܂����B�Εď]���ȊO�̐����I�I���������邩�ǂ������ᖡ�������Ƃ��Ȃ������悤�ł����B�ł��A�Ⴆ�A�C�M���X�̐����w�҂Ɂu�Εē����ȊO�̈��S�ۏ�̑I�����v��u���Ă��A�h�C�c�̐����w�҂Ɂu�d�t�ȊO�̈��S�ۏ�̑I�����v��u���Ă��A�u�l�������Ƃ��Ȃ��v�Ɠ����邱�Ƃ͂��肦�Ȃ��Ǝv���܂��B�ӂ��́u���܂���d�g�݈ȊO�̉\���v���A�W�R�����ǂ�قǒႭ�Ă��A�ꉞ�͍l���Ă����B���{�l�������O��헪�ɂ����āu���ē�����v�A�܂�Εď]���ȊO�̂����Ȃ�I�����ɂ��Ă����̉\���⍇�����ɂ��čl���Ȃ��B����͂����炩�ɕa�I�ȏnj�ł��B
�Εď]�������Ɛ헪�ł͂Ȃ��A�����̕a�I�Œ��ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��킩�����̂́A���R����̕��V�Ԋ�n�ړ]�ɂ��Ă̔������߂��鑛���̂Ƃ��ł��B�l�́A���̂Ƃ��A�𒍎����Ă��āA�ق�Ƃ��ɂт����肵���B���̂Ƃ����A���{�̑傫�ȓ]���_�ł͂Ȃ��������v���܂��B
���R�́A���V�Ԋ�n���ł����獑�O�A���߂Č��O�Ɉړ]�������ƌ������킯�ł��B�����ɂ�����ČR��n�̕��S���y���������B�ł����獑�O�Ɉڂ��ė~�����A�����������B�O���̌R�����P��I�ɍ����ɒ������Ă���Ƃ����̂́A�ǂ̎匠���ƂɂƂ��Ă��p�����������Ƃł��B�ӂ��͂��������܂��B�O���̊�n���펞��������̂͒N�����Ă��R���I�]�����̃|�W�V����������ł��B
�t�B���s���̓A�����J�̌R���I�����I�ȃ|�W�V�����̍��ł�������ǁA���@���������ĊO���R�̒�����F�߂Ȃ����Ƃɂ��܂����B���̂����ŕČR�̓N���[�N�A�X�[���B�b�N�Ƃ����A�����J�ő�̊C�O��n����̓P����]�V�Ȃ�����܂����B�؍��ł��A����������n�^����W�J�������ʁA�݊ؕČR��n�͑啝�ɏk������܂����B�\�E���s���ɂ��������R��n���ړ]������ꂽ�B
�ł��A���{�̃��f�B�A�́A�؍���t�B���s���ɂ����锽��n�^�����قƂ�Ǖ��܂���ł����B�l�͂܂������m��Ȃ������B�ȑO�A�C�O���h������Ƃ����Ƃ���ɌĂ�ču�������Ƃ��ɁA�i������Ă����C�M���X�l�W���[�i���X�g����u�؍��̔���n�^���ɂ��Ă͂ǂ��v���܂����v�Ǝ��₳��āA�u���̘b��m��܂���v�Ɠ�������A�����ꂽ���Ƃ�����܂��B�u���S�ۏ��O���̂��Ƃ�b���Ă���l�Ԃ��A���̊�n����m��Ȃ��̂��H�v�ƁB�ł��A���{�̃��f�B�A�ŁA����Șb�������Ƃ��Ȃ������B
�؍��ł́A�����ɂ킽�锽��n�^���̌��ʁA�݊ؕČR��n�͏k������Ă��܂��B���{�ł́A���ς�炸�u�����L���ɔ����āv�Ƃ������R�ʼn���̌R���I�d�v���͕ς��Ȃ��Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ�V���̎А��͏����Ă���B�ł��A�u�����L���̔����v������قNji�قł���Ƃ����̂Ȃ�A���N�����̕ČR��n���k������Ă��闝�R�������ł��Ȃ��B����قǖk���N�̌R�����X�N�������Ȃ�A�ނ���ČR�����ׂ��ł��傤�B������A�������Ղ��ꂽ���Ȃ��̂ŁA���{�ł͓��A�W�A�ł̕ČR��n�k���̎������̂��̂�����Ȃ��B
����ɂ�₱�����̂́A�؍��̏ꍇ�́A��������ĕČR��n�͏k�����邯��ǂ��A�펞��퓝�����͂܂��A�����J�Ɏ����Ă��Ă�����Ă���Ƃ������Ƃł��B�܂�A�ČR��n�͎ז�������o�čs���Ă��炢��������ǁA�k���N�ƈ��\����Ƃ��ɂ͕ČR�ɏo�����ė~�����̂ŁA�펞��퓝���������̓A�����J�ɉ������Ă���B��������ăA�����J���X�e�[�N�z���_�[�Ɋ������ނƂ����A���Ȃ�g���b�L�[�ȕĊ؊W��W�J���Ă��܂��B
�ł��A����͎匠���ƂƂ��Ă͓��R�̂��ƂȂ̂ł��B�ČR�͕����͂���Ǝז������A��펞�ɂ͕K�v�ɂȂ�B�؍����̎��ȓs���ł�����������Ȃ��Ƃ������Ă���B�匠���ƂƂ����̂́u�����������́v�ł��B�����̍��v��D�悵�ď���Ȃ��Ƃ��������Ƃ̂ł��鍑�̂��Ƃł��B�؍��͂��̓_�Ŏ匠���Ƃł��B
�t�B���s���������ł��B��U�͕ČR��n���ז�������o�čs���ƒǂ��o���Ă����Ȃ���A��V�i�C�Œ����Ƃ̗̓y��肪�N���Ă���ƁA��͂�߂��Ă����ƌ����n�߂��B�����Ă��邱�Ƃ͎����т��Ă��Ȃ��悤�ł����A�����т��Ă���B�����̍��v���ŗD�悵�Ă���B
���̒��ɂ����āA���{�������Ⴄ�B���ꂼ��̍��������̍��v��Nj����Ă����āA�����̍��v�Ƃ̊Ԃł��荇�킹�����Ă����āA���Ƃ��ǂ����T���Ă����B���ꂪ�{���̎匠���Ɠ��m�̊O�����̂͂��ł����A���{�����̓A�����J����ɂ��������Q�[�������Ă��Ȃ��B�A�W�A�������A�����J�ƌܕ��ŃV�r�A�ȐՂ����Ă��钆�ŁA���{�������A�����J�ɉ����v�����Ȃ��ŁA�����B�X���X�Ƃ��̎w���ɏ]���Ă���B����ǂ��납�A�ߗׂ̍����A�����J����ɓ��X�ƃp���[�Q�[����W�J���Ă���Ƃ����j���[�X���̂��A���{�ł͂قƂ�Ǖ���Ȃ��B
���̔��R����̌��ł�����ǂ��A���R����́A�����ɕČR��n�A�O���R�̊�n������Ƃ������Ƃ͖]�܂������Ƃł͂Ȃ��ƌ������킯�ł��B������O�ł���ˁB�匠���ƂƂ��ẮA���R�A�����������ׂ��ł���B����̏ꍇ�́A���{���y�̂O�D�U���̖ʐςɁA�����̎��܁��̕ČR��n���W�����Ă���B����ُ͈�Ƃ������Ȃ��B���̎��Ԃɑ��āA��n���k�����ė~�����A�ł����獑�O�ɓP�����Ă������������Ƃ������Ƃ�v������͎̂匠���ƂƂ��Ă͓��R�̂��ƂȂ킯�ł��B����ǂ��A���̔����ɑ��Ă͏W���I�ȃo�b�V���O������܂����B���ɊO���ȂƖh�q�Ȃ́A�̑�����������A���ʓI�Ɏ̑ސw�̗�����������B
�A�����J����u���R�Ƃ����̂͂ǂ����A�����J�ɂƂ��Ė��ɗ����Ȃ��l�Ԃ�����A�̍����痎�Ƃ��悤�Ɂv�Ƃ����w�����������Ɩl�͎v���Ă��܂���B����ȓ������ɂȂ�悤�Ȏw�������Ȃ��Ă��A���R���ł���ƁA�A�����J�̍��v�����Ȃ��郊�X�N�����邩��A�������艺�낻���Ƃ������Ƃ��l���鐭���Ƃ⊯��������������{�����ɂ��邩��ł��B���f�B�A���A���A�u�A�����J�̐M�������������R�͎��߂�ׂ����v�Ƃ��������Ă��܂����B�Ȃ��A���{�̎��ČR��n�̏k����ړ]�����߂����Ƃ����{�̍��v�Ȃ����ƂɂȂ�̂��A�l�ɂ͗��R���킩��܂���ł����B
���̎����́u�A�����J�̍��v���ő剻���邱�Ƃ��A���Ȃ킿���{�̍��v���ő剻���邱�ƂȂ̂ł���v�Ƃ����M�߂���{�̎w���w���[�����ʉ����Ă��܂����A�ނ�̒m�I���p�̓T�^�I�ȏǏ����Ǝv���Ă���܂��B
�@
�f��ē̃I���o�[�E�X�g�[�����A�Q�O�P�R�N�ɓ��{�ɗ��āA�L���ōu�����������Ƃ�����܂����B��������{�̃��f�B�A�͍u�����e�ɂ��Ă͂قƂ�Ǖ��܂���ł����B�I���o�[��X�g�[�����u���Ō������̂͂����������Ƃł��B
���{�ɂ͂��炵������������A���{�̉f������炵���A���y�����p�����炵�����A�H���������炵���B����ǂ��A���{�̐����ɂ͌���ׂ����̂������Ȃ��B���Ȃ����͎��ɑ����̂��̂𐢊E�ɂ����炵������ǂ��A���{�̂���܂ł̑�����b�̒��ŁA���E���ǂ�����ׂ����ɂ��ĉ����Ƃ���������l�͂��Ȃ��B��l�����Ȃ��BDon�ft
stand for anything�@�ނ�͉����\���Ă��Ȃ��B�����Ȃ��`���f�������Ƃ��Ȃ��B���{�͐����I�ɂ̓A�����J�̑���(client
state)�ł���A�q����(satellite state)�ł���A�ƁB����͓��{�̖{��������ƏՂ������t�������Ǝv���܂��B�A�����J�̃��x�����h�̐l�����̂��ꂪ�����Ȍ����ł��傤�B
���{�͂������ɂ��܂��܂ȗ͂������Ă���B�o�ϗ͂������͂�����B���a���@���ێ����āA�푈�ɃR�~�b�g�����ɗ����B����ǂ��A���ێЉ�Ɍ����Ĕ��M����悤�ȃ��b�Z�[�W�͉��ɂ������Ă��Ȃ��B�A�����J�ɒǐ�����Ƃ����ȊO�̓Ǝ��̐����I�������������Ă��Ȃ��B����́A�A�����J�l�݂̂Ȃ炸�A���ێЉ�猩���Ƃ��̓��{�ɑ���T�^�I�Ȉ�ۂł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
���̂Ƃ��A�I���o�[��X�g�[���́u���������A��ʁA�I�o�}�ɋt����Ď�ɂ��ꂽ������b����l�������v�ƌ����Ă���܂�������ǂ��A����͂������I���o�[�E�X�g�[���̊��Ⴂ�ł���܂��B�ʂɃI�o�}�ɋt���������A�I�o�}�ɂ���Ď�ɂ��ꂽ�킯�ł͂Ȃ��āA�ނ���ɂ����͓̂��{�l����������ł��B
�����{�̍��v���\���āA�f���ɍ��y���������A�匠���������Ƃ������Ƃ��A�����J�ɓ`������A����Ă������ē��{�l�������ׂ����Ƃ����������̂��̂����{�̜늳�����a�̒������Ɩl�͎v���܂��B�A�v���[�`�͐ٗ��������m��Ȃ����A�̎咣�͐������Ƃ����i��̘_�w�������f�B�A�͖l�̒m����肠��܂���ł����B�A�����J�̐M���𗠐�悤�Ȑ����Ƃɍ����͑����Ȃ��Ƃ����̂��قƂ�ǂ��ׂẴ��f�B�A�̘_���ł����B�u������ƁA����͂���������Ȃ����v�ƌ����l���قƂ�ǂ��Ȃ��������Ƃ�l�́u���������v�Ǝv���܂����B
�匠���Ƃ��z������̂́A�܂����y�̕ۑS�A�����̈��J�A�ʉ݂̈���A�O���⍑�h�ɂ��Ă̍œK����̑I���A�������������Ƃ��Ǝv���܂��B�匠�̑������ł���u���y�̉v��v�������]�����̎��A���y���̂��Ă���@�卑�ɂ���Ăł͂Ȃ��āA��̂���Ă��鑤�̎����̊�������Ƃ�W���[�i���X�g�ɂ���čU������B����͓|���I�Ƃ���������܂���B
�Ȃ����̂悤�ȕa�I�X�����������̂��B����́u�Εď]����ʂ��Ă̑ΕĎ����v�Ƃ����s�풼��ɍ̗p���ꂽ�o�������A���̗L�����ɂ��Ă��̂Njᖡ���邱�ƂȂ��A�@�B�I�ɂ��܂��ɓK�p�������Ă��邹�����Ǝv���܂��B�ł��A�l���Ă��݂Ă��������B�P�X�V�Q�N�̉���Ԋ҂����́A�����S�Q�N�o���Ă���B���̊ԁA�A�����J������{���D�҂������͉̂���Ȃ��킯�ł��B�S�Q�N�ԁA���{�͑Εď]����ʂ��ĉ���匠�����Ă��Ȃ���ł��B�Εď]���͓��{�ɂ��̂S�Q�N�ԁA�������ׂ��ʎ��������炵�Ă��Ȃ��Ƃ����������u�Εď]���_�ҁv�͂ǂ��]�����Ă���̂��B���̂܂܂���ɂ����T�O�N�A�P�O�O�N���́u�犔�ғe�v�헪���p�����ׂ����Ƃ������f�̍����͉��Ȃ̂��B����𑱂���A������̊�n�͓P�������̂��A���c��n�͖߂��ė���̂��B������������Ȃ��܂܂ɁA�O��P����Ƃ����O���`�ɂ���đΕď]���������Ă���B
�A�����J���猩��ƁA���{���̃v���C���[�̎����ς�����Ƃ������Ƃ́A��������i�K�Ō����Ă���Ǝv����ł��B����܂œ��{�́A����Ȃ�Ƀ^�t�ȃl�S�V�G�[�^�[�ł������B�Εď]���̃J�[�h������ꍇ�ɂ́A����ɑ��錩�Ԃ��v�����Ă����B�������A����i�K����A�Εď]�������x�����A�Εď]���I�ȃ}�C���h�������Ă���l�Ԃ����������{�����̃q�G�����L�[�̒��ŏo���ł��Ȃ��悤�Ȏd�g�݂ɂȂ����B���ꂩ��A����ɂ���v���C���[���ς�����Ƃ������ƂɁA�A�����J�͂����C�Â��Ă���Ǝv���܂��B
���Ẵv���C���[�͑Εď]����ʂ��āA���{�̍��v�������o�����Ƃ��Ă����킯�ł�����ǁA���܂̃v���C���[�����͈Ⴄ�B�A�����J�̍��v�Ɠ��{�̍��v�Ƃ����{����������͂��̂��̂��u���荇�킹��v���Ƃł͂Ȃ��A�A�����J�̍��v�傳����Ɓu�킪�g�ɂ悢���Ƃ��N����v�Ƃ����ӂ��ɍl����l����������̗v�H�ɗ����Ă���B
���ɁA����܂őΕď]���H�����^�����ƂȂ��Ђ������Ă��������Łu�����̒n�ʁv���l�����������ɂ���킯�ł�����A�ނ炪���ꂩ����Εď]���H�����Ђ����邱�Ƃ͂Ƃǂ߂������B�ނ�ɂ����ẮA���̂܂ɍ��v�Nj��Ǝ��ȗ��v�̒Nj����I�[�o�[���b�v���Ă��܂��Ă���B���̂��߂̑Εď]�����Ƃ����ƁA�Ƃ肠�����A��������Ɓu�킪�g�ɂ͂悢���Ƃ��N����v�̂��m��������ł��B
�A���n�ɂ����āA�A���n���Z���ł���ɂ�������炸�A�@�卑���ɂ������āA���̕X���͂������ɁA�����I�o�ϓI�Ȍ��Ԃ��v��������̂͐��������Ɂu���فv�ƌĂ�܂����B���̓��{�̎w���w�́A�@�卑�ւ̏]���I�|�[�Y��ʂ��āA���ȗ��v�傳���悤�Ƃ��Ă���_�ɂ����āA���łɁu���ٓI�v�ł���ƌ��킴��Ȃ��Ɩl�͎v���Ă��܂��B
�ł́A���̌�A���{�͈�̂ǂ�����Ď匠�ւ̓������ł������炢���̂��B
���A�A�����J���猩�āA���{�Ƃ����͔̂��ɕs���ȍ��Ɍ����Ă���Ǝv���܂��B
���Ă̋g�c�Έȗ��̓��{�̃J�E���^�[�p�[�g�́A��{�I�ɓ��{�̍��v����邽�߂ɃA�����J�ƌ����Ă����B���̓��@�͖��m�������B����ǂ��A����i�K����A�����łȂ��Ȃ��Ă��Ă��܂����B�Εď]���헪���ʏ]���w�̕��G�ȃ^�N�e�B�N�X�ł��邱�Ƃ��~�߂āA�^�����Ȃ��u�����v�ƂȂ��Ă��܂����B����ɂ���ē��{�̍��v�����������債�Ȃ��ɂ�������炸�A�Εď]�����邱�ƂɒN�����ł��Ȃ��B���������d�g�݂��l�\�N�ԑ����Ă���B
��������ƁA�A�����J�͓��{�̐����Ƃ��ǂ����邩�B������ꍇ�A���{�̑�\�҂������̍��v�債�悤�Ǝv���Ă���̂ł���Ȃ�A�����œW�J����Q�[���ɂ͍�����������킯�ł��B�A�����J�̍��v�Ɠ��{�̍��v�Ƃ����̂́A���Q����������_������A��v����_������B���̂��肠�킹������̂��O���������B�Ƃ��낪�A���̂܂ɂ��A�����炩�ɓ��{�̍��v���Q���邱�Ƃ��m���ȗv���ɑ��Ă��A���{������R���Ȃ��Ȃ��Ă����B���̂ӂ�܂��͔ނ炪���{�̍��v���\���Ă���ƍl����Ɨ����ł��Ȃ��B���{�����Ă���l�������A�����̍��v�̑���ɊS���Ȃ��悤�Ɍ�����킯�ł�����B
�Ⴆ�A����閧�ی�@�ł��B����閧�ی�@�Ƃ������̂́A�v����ɖ��卑�Ƃł�����{���A�����ɗ^�����Ă����{�I�Ȑl���ł��錾�_�̎��R�𐧖悤�Ƃ���@���ł��B�����ɂƂ��Ă͉��̗����Ȃ��B�Ȃ��A���̂悤�Ȕ�����I�Ȗ@���̐�������s�̌������Ă܂ŋ}���̂��B
���R�́u���̂悤�Ȗ@�����Ȃ���A�����J�̌R�@���R��āA���Ă̋����I�ȌR�����̎x��ɂȂ�v�Ƃ������Ƃł����B�A�����J�̍��v����邽�߂ɂł���A���{�����̌��_�̎��R�Ȃǂ͗}�����Ă��\��Ȃ��A�ƁB���{�����͂��������ӎv�\���������킯�ł��B�����āA�A�����J�̌R�@����邽�߂ɓ��{�����̊�{�I�l���𐧖܂����ƃA�����J�ɐ\���o���킯�ł��B���{�̍����S�̗̂��v�Ȃ����Ƃ�ʂ��āA�A�����J�̌R�@����肽���A�ƁB����ꂽ�A�����J���炵�Ă݂���A�u�����A�����ł����B�����A�ǂ����v�Ƃ����ȊO�Ɍ��t���Ȃ��ł��傤�B�������ɂ�������������Ē�����̂͂܂��Ƃɂ��肪�������Ƃł͂��邦��ǁA��̉��œ��{���{������Ȃ��Ƃ������Ă���̂��A���͂悭�킩��Ȃ��B�Ȃ����{�͍����̊�{�I�l���̐���Ƃ����悤�ȁu�]���v���A�����J�̂��߂ɕ�����̂��B
�w�X��̐푈�_�x�i�~�V�}�Њ��j�ɂ������܂�������ǂ��A�����������Ƌ@���Ƃ����̂́A���{�̃g�b�v���x������R�k���邩��댯�Ȃ킯�ł��B�������̂Ƃ���A�C�M���X�̃L���E�t�B���r�[�����Ƃ����̂�����܂����BMI�U�̑\�A���̕����������L���E�t�B���r�[���A�����ƃ\�A�̃X�p�C�ł����āA�C�M���X�ƃA�����J�̑\�A���͂��ׂă\�A�ɓ������������Ƃ������ő�̃X�p�C�����ł��B����ȗ��A����@�ւ̒�������̋@���R�k�͂ǂ�����Ζh���邩�Ƃ����̂��A�C���e���W�F���X�ɂ��čl����ꍇ�̍ő�̉ۑ�Ȃ킯�ł��B
���̑O�ɂ��A�C�M���X�ł̓v���q���[�������Ƃ������̂�����܂����B���R��b�����t�w�ɂ��낢��ƌR�@��R�炵�Ă��܂����B�ł��A�s���[�g�[�N�ŘR���閧�ƁA����@�ւ̃g�b�v����R���閧�ł͋@���̎����Ⴂ�܂��B�ł�����A�ق�Ƃ��ɐ^���ɒ�����A�h���̖����l����Ƃ���A�ǂ�����č��Ƃ̒����ɓ��荞��ł��܂����u���O���v����̏��R�k��h�����Ƃ������Ƃ��ً}�̉ۑ�ɂȂ�͂��ł��B
����ǂ��A����̓���閧�ی�@�́A���E���o�������j��ň��̃X�p�C�����ɂ��Ă͑S���z�����Ă��Ȃ��B�L���E�t�B���r�[�����̂悤�Ȃ������ł̋@���R�k���ǂ�����Ėh�����Ƃ������ƂɊւ��Ă͒N����b�������g���Ă��Ȃ��B�����������Ƃ́u�Ȃ��v�Ƃ������Ƃ�O��ɖ@�����N�Ă���Ă���B�܂�A�����ɁA���{�Łu�L���E�t�B���r�[�^�̒����v���s���Ă���l�Ԃɂ��ẮA�u���̂悤�Ȃ��̂͑��݂��Ȃ��v�Ƃ���Ă���킯�ł��B�ނ�͖����i���Ƀt���[�n���h��ۏ��ꂽ���ƂɂȂ�B���Ȃ����̂͒T�����悤���Ȃ��ł�����B
���ɍ��ƌ��͂̒������獑�Ƌ@�����R�k���Ă���Ƃ������Ƃ́A���{�ł͂������ɓ���I�ɍs���Ă���Ɩl�͎v���Ă��܂��B�ǂ��ɗ���Ă��邩�B�������A�����J�ɗ���Ă���B�����Ƃł������ł��W���[�i���X�g�ł��A�m�����̋@�����A�����J�Ƃ̊ԂɎ�茋���ꂼ��́u�p�C�v�v�ɗ�������ł���B���ꂪ�A�����J�̍��v�傳����^�C�v�̏��ł���A���̌��Ԃ�͔ނ�Ɍl�I�ȕƂ��ă��^�[������Ă���B���ʓI�ɐ��{������ƊE���ɂ�����ނ�̒n�ʂ͏㏸����B�����āA�ނ炪�A�����J�ɗ����@���͂܂��܂����̍������̂ɂȂ�B���������u�E�B���E�E�B���v�̎d�g�݂������o���オ���Ă���A�l�͂����m�M���Ă��܂��B����閧�ی�@�́A�u�@���R�k�h�~�v�ł͂Ȃ��A�ނ�́u�@���R�k�v�V�X�e������茘�S�Ȃ��̂Ƃ��邽�߂̖@���ł��B�A�����J�̍��v����̂��߂ɐ��肳�ꂽ�@���Ȃ�ł�����A���̖@�����A�����J�̍��v����̂��߂̋@���R�k�������ł���͂����Ȃ��B
����閧�ی�@�ɃA�����J�������Ȃ������Ƃ����̂́A�������̊�{�I�l���𐧖Ă܂ŃA�����J�̌R�@�����Ƃ����@������̎�|�ƁA���͒�������̏��R�k�ɂ��Ắu���̂悤�Ȃ��̂͑��݂��Ȃ��v�Ƃ����O��ɗ��@�����ɍD�������������ł��B���ꂩ���A���{���{�̒�������ǂ̂悤�Ȃ������ō��Ƌ@�����A�����J�ɘR�k���悤�Ƃ��A��������u����閧�v�Ɏw�肳�ꂽ���ɂ��ẮA���ꂪ���ł��邩�A�N��������ǂ���舵�������A���ׂĂ��B������Ă��܂��B�ǂ�قǔ閧���R�k���Ă��A�����N�ɂ��킩��Ȃ��B
�����A�l���A�����J�̍����Ȃ̖�l��������A���{�l�͓������������Ȃ����̂��Ǝv�����͂��ł��B�������ɃA�����J�ɂƂ��Ă͂��肪�������\���o�ł��邪�A���ł���Ȃ��Ƃ�����̂����킩��Ȃ��B�ǂ��l���Ă݂Ă����{�̍��v�ɑS��������Ƃ��낪�Ȃ��B���������h���̂��߂̖@���Ƃ��ċ@�\���������Ȃ��B���̂悤�ȃU���@�𐧒肷��㏞�Ƃ��āA�������̊�{�I�l����}�����悤�Ƃ����B���_�̎��R�𐧖Ă܂ŁA�A�����J�ɑ��ăT�[�r�X������B�������ɃA�����J���Ƃ��Ă͒f�郍�W�b�N������܂���B�킪���v���������`�̗��z�̕����������A����Ȗ@���͍��̂��~�߂Ȃ����Ƃ����悤�Ȃ��ꂢ���Ƃ̓A�����J���{��������͂����Ȃ��B���{����̐\���o��f�郍�W�b�N�͂Ȃ�����ǁA����ł����{�l�������l���Ă��邩�͂킩��Ȃ��B���������A����閧�ی�@�œ��{�l�̒N���ǂ��������v��̂��H
���{���{�����{�̍��v�Ȃ��悤�Ȗ@�����u�A�����J�̂��߂Ɂv���������̂��Ƃ���A����͍��v�ȊO�́u���Ԃ�v�����߂ĂȂ��ꂽ�Ƃ������ƂɂȂ�B���v�łȂ��Ƃ���Ή����B�������̉����Ƃ��A�����Ƃ⊯���l�̎��ȗ��v�̑���Ƃ��������̂����߂ĂȂ��ꂽ�Ƃ݂Ȃ������Ȃ��B
���ɁA�č����Ȃ͂������f���Ă���Ǝv���܂��B���{���{����́u�T�[�r�X�v�͂��肪������邯��ǁA���̂悤�ɂ��Ă܂ŃA�����J�ɂ����˂��Ă��鐭���Ƃ⊯�����u���{���v�̑�\�ҁv�Ƃ��ċ����邱�Ƃ͂��Ȃ��A�ƁB
�W�c�I���q���������ł��B�W�c�I���q���Ƃ����̂́A���x�������Ă��܂�����ǂ��A�����������u���l�̌��܂������v�̂��Ƃł��B���Ȃ��Ƃ�����܂ł̔�������������́A�n���K���[�����A�`�F�R�X���o�L�A�����A�x�g�i���푈�A�A�t�K�j�X�^���N�U�ȂǁA�\�A�ƃA�����J�Ƃ�����咴�卑���A�����́u�V�}���v�ɂ�����S���������ΐ��͂ɂ���ē|���ꂻ���ɂȂ����Ƃ��ɁA�u�Ă�����v���邽�߂Ɏ��R�𓊓�����Ƃ��̖@�I�����Ƃ��Ďg�������Ⴕ���Ȃ��B
���œ��{���W�c�I���q���Ȃs�g��������̂����A�ł�����l�ɂ͂����ς�킩��Ȃ��B���������ǂ��ɓ��{�́u�q�����v��u�]�����v������̂��B�C�O�̂ǂ����ɓ��{�̘��S����������Ƃ����̂ł���A�b�͂킩��B���̐e�����������剻�^���œ|�ꂩ���Ă���B���悤���Ȃ�����A������ƌR�����o���Ĕ��ΐ��͂͂Œe�����āA�����̂Ă���������Ă��悤�Ƃ����̂ł���A�Ђǂ��b�ł͂��邯��ǂ��A�b�̋ؖڂ͒ʂ��Ă���B�ł��A���{�ɂ͂���ȁu�V�}�����v�̍��Ȃ���܂���B
���ǁA�W�c�I���q���̍s�g�Ƃ����̂́A�����I�ɂ̓A�����J�������́u�V�}�����v����߂�Ƃ��ɂ��̊C�O�h���ɓ��{���������Ă����āA�A�����J�̉����ŌR���s�����Ƃ�Ƃ����������������肦�Ȃ��B�A�����J�̏ꍇ�A�����̎�҂�������A�W�A��A�t���J�Ŏ��ʂƂ������Ƃɂ����ς����Ȃ��Ȃ��Ă���B�Ӗ����킩��Ȃ�����B�ł��A�C�O�̕����ɂ͉�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���������Ȃ�����A���Ƃ����āu���҂̊O�����v���͂����Ă���B���l��s�@��������A�~�T�C���������肵�Ă���Ƃ����̂́A��{�I�ɂ͐��g�̐l�Ԃ̌��𗬂������Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�U���͂���������ǂ��A���͗��������Ȃ��B������A���Ԃ̌x����Ђւ̐퓬�̃A�E�g�\�[�V���O�����Ă��܂��B����͂܂��Ɂu���҂̊O�����v�ɑ��Ȃ�܂���B�������ɁA����ɂ���Đ펀�҂͌y�������B�ł��A���̑��蔜��ȍ�����̕��ׂ��������B�x����ЁA�v����ɗb����Ђł�����ǁA�߂��Ⴍ����Ȓl�i��v�����Ă��܂�����B�A�����J�́A���̌o�ϓI�ȕ��S�ɑς��邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B
�����ɓ��{���W�c�I���q���̍s�g�e�F���t�c���肵�܂����ƌ�������A�A�����J�����炵�Ă݂�Ƒ劽�}�Ȃ킯�ł��B����܂Ŗ��Ԃ̌x����ЂɃA�E�g�\�[�V���O���āA����ȗ����𐿋�����Ă���d�����A���ꂩ�玩�q���������ł���Ă����킯�ł�����B����Ă��Ȃ��b�Ȃ킯�ł���ˁB�u�₠�A���肪�Ƃ��v�ƌ����ȊO�Ɍ��t���Ȃ��B
�����A�u�₠�A���肪�Ƃ��v�Ƃ͌����Ȃ���A���œ��{������Ȃ��Ƃ����Ă����̂��A���̓��@�ɂ��Ă͂���ς藝��s�\�ł���B
�A�����J�������Čق��Ă���b���̑���ɖ����̎��q�������g���Ă����ł��Ƃ����I�t�@�[����{���{�͂��Ă��Ă���킯�ŁA���ꂪ�ǂ����ē��{�̍��v����Ɏ����邱�ƂɂȂ�̂��A�A�����J�l���l���Ă��킩��Ȃ��B
�܂�A�m���ɓ��{���{������Ă��邱�Ƃ̓A�����J�ɂƂ��Ă͂��肪�������Ƃł���A�A�����J�̍��v�𑝂����Ƃł͂������ǂ��A����͏��������{�̍��v�𑝂��悤�ɂ͌����Ȃ��B���ꂩ�玩�q�����C�O�ɏo�Ă����āA���q�����������Ŏ�������B���邢�́A���n�l���E���A�����Ă����肵�āA���ʓI�ɓ��{���̂��̂��e�����X�g�̕W�I�ɂȂ�Ƃ����傫�ȃ��X�N������邱�ƂɂȂ�킯�ł��B�푈�ɃR�~�b�g���āA���ʓI�Ƀe���̕W�I�ɂȂ邱�Ƃɂ���Đ�����u�J�E���^�[�e���̃R�X�g�v�͋���Ȋz�ɂ̂ڂ�܂��B���̓��{�̓e����̂��߂̎Љ�I�R�X�g���قƂ�Ǖ��S���Ă��Ȃ��ōς܂��Ă���B����������Ȃ�S�����Ԃ낤�Ƃ����킯�ł�����A�A�����J�Ƃ��Ắu�₠�A���肪�Ƃ��v�ȊO�̌��t�͂Ȃ�����ǁA�u�N�A�����l���Ă���Ȃ��Ƃ���v�Ƃ����^�O�͕��@�ł��Ȃ��B
�l�͂����������A�����J�����Ȃ̏���l��������Ƃ����z��ŕ����l�����ł�����ǂ��A��i����u���c�N�A���{�͓���閧�ی�@�Ƃ����A�W�c�I���q���s�g�e�F�Ƃ����A�A�����J�̂��߂ɂ��낢�낵�Ă���Ă������ǁA�ǂ�������{�̍��v�Ɏ�����I���Ƃ͎v���Ȃ��B�����������{���{�͉��ł���ȕs�𗝂Ȍ��f���������̂��A�N�ɐ����ł��邩�ˁv�Ɩ��ꂽ��A�ǂ������邩�B
�������ɁA���v�̑���̂��߂ł͂Ȃ��ł��ˁB����Ԋ҂܂ł̑Εď]���H���ł���A���{���]�������Ƃɂ���ăA�����J��������������o���Ƃ������Ƃ�͂������킯�ł�����ǂ��A���̊Ԃ̑Εď]�����݂Ă���ƁA�����߂����Ă���Ȃ��Ƃ����Ă���̂��A���ꂪ�悭�����Ȃ��B���Ԃ�A�ނ�͍��v�̑�������߂Ă���̂ł͂Ȃ���Ȃ����ł��A�ƁB�������\����Ǝv���܂��B
���A���{�Ő��肵�Ă���l�����Ƃ����̂́A���v�̑���̂��߂ɂ���Ă���̂ł͂Ȃ��āA�h���X�`�b�N�ȃq�G�����L�[�̒��ŏo���Ǝ��ȗ��v�̊g��̂��߂ɂ������Ă���悤�Ɍ����܂��B�܂�A�u�����������A�����J�ɔ����āA���̈ꕔ�����ȗ��v�ɕt���ւ��Ă���v�Ƃ����ӂ��Ɍ����Ă�̂��K�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��A�ƁB�@
���������Ƃ����̂́A���{�����ꂩ��S�N�A��S�N�������߂̃X�g�b�N�̂��Ƃł��B����͎�𒅂��Ă͂����Ȃ����̂ł��B���吧�Ƃ����d�g�݂����������A���y�����������A�����̌��N�����������A�`�������������ł��B�ł��A���̓��{���{�̓X�g�b�N�Ƃ��ĕێ����ׂ��������������X�Ə��i�����Ďs��ɗ����Ă���B����𐢊E���̃O���[�o����Ƃ��H����������ɐH���r�炷���Ƃ��ł���悤�Ȏd�g�݂���낤�Ƃ��Ă���B����Ȃ��Ƃ�����A���{�S�̂Ƃ��Ă̍��������͑��Ȃ��A�����̍��v�͒������Ă䂭�킯�ł�����ǂ��A�������͂�����哱���Ă���B�ނ�̂��������C�Ⴂ���݂��s���@�Â��Ă�����͉̂����ƌ�������A���ꂪ���v�̑���Ɍ��т���H�����݂��Ȃ��ȏ�A�������~�̒Nj��ł����Ȃ��킯�ł��B
�����I�A���œI�ȑΕď]������̍����I�ȍ��������߂悤�Ƃ���A����́A�Εď]���h�̐l�������g����������l�I�ɗ��v����d�g�݂ɂȂ��Ă��邩��Ƃ����ȊO�Ɂu�����Ȃ̖�l�ɂȂ����Ƒz�����Ă݂����c�v�̃��|�[�g�̌��_�͂���܂���B
�Εď]���������قǁA�Љ�I�i�t�����オ��A�o�����A�c�ȂA��w�̃|�X�g�ɂ�����A���{�ψ��ɑI��A���f�B�A�ւ̘I�o�������A�l���Y��������A���������d�g�݂����̂S�Q�N�Ԃ̊Ԃɓ��{�ɂ͂ł��Ă��܂����B���́u�|�X�g�V�Q�N�̐��v�ɋ��������l�X��������{�ł͎w���w���`�����Ă���A������N�Ă��A�r�W�l�X���f����n��o���A���f�B�A�̘_�������肵�Ă���B
�ӂ��u�����������Ɓv�͎匠���Ƃł͋N����܂���B����͓T�^�I�ȁu���فv�I�ȍs���l��������ł��B�A���n�ł����N����Ȃ��B���قƂ����̂́A�����̍��Ȃǂ������č\��Ȃ��A���������悯�����ł����Ƃ����l����������l�����̂��Ƃł��B���{�Łu�O���[�o���l�ށv�ƌĂ�Ă���̂́A���������l�����̂��Ƃł��B���{�I�����ł́u�O���[�o���v�Ƃ������t�����ׂāu���فv�Ƃ������t�ɒu�������Ă��Ӗ����ʂ�悤�ȋC�����܂��B���ȏȂ́u�O���[�o���l�ވ琬�v�헪�Ȃǂ́u���ِl�ވ琬�v�Ə���������������قǂ������肵�܂��B
���{����Ƃ����l�́A�ꉞ�A�����{�����Ƃ̂c�m�`�������͈����p���ł��܂�����A�������ɂׂ�����̑Εď]���ł͂���܂���B���S�Ƃ��ẮA�ǂ����őΕĎ������ʂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���Ă͂���B����ǂ��A������u���v�̑���v�Ƃ����������ł͂����l�����Ȃ���ł��B�����������G�ȃQ�[�����ł��邾���̒m�͂��Ȃ��B
������A���{����͔��ɃV���v���ȃQ�[�����A�����J�Ɏd�|���Ă���B�A�����J�ɑ��Ĉ�]���I�Ȑ�������{������ɂ́A��A�����J�������邱�Ƃ�����B
�������̂Ƃ���A�W�c�I���q�������̌�ɁA�k���N�ւ̌o�ϐ��ق��ꕔ�������܂����B����̒���^�m����������ĕӖ�Â̖��ߗ��Đ\���̏��F�����t������͂����ɖ����_�ЂɎQ�q���܂����B�܂�A�u�A�����J����Ԃ��Ɓv����������́A�u�A�����J�������邱�Ɓv������B�����˂�����ɑ��ށB���ꂪ���{�W�O�̒��ł́u�ʏ]���w�v�Ȃ̂ł��B���Ă̍��v�̂��Ƃ�ł͂Ȃ��A�A�����J�̍��v�傳�����㏞�ɁA�u�ނ��l�I�ɂ��������ƂŁA�A�����J���}���肻���Ȃ��Ɓv������Ă݂���B��ϓI�ɂ́u����Ōܕ��ܕ��̌������Ă���v�Ɣނ͖������Ă���̂��낤�Ǝv���܂�����ǁA�����Q�q��k���N�ւ̏������Ȃ����{���v�̑���Ɍ��т��̂��ɂ��Ă̌��͂��Ȃ��B�ނɂƂ��Ắu���������������ƂŁA�A�����J���}���肻���Ȃ��Ɓv�ł͂���̂ł��傤����ǁA���ꂪ���{�̍��v���Ɏ����鐭�����f�ł��邩�ǂ����͋ᖡ���邱�Ƃ������Ă��Ȃ��B
�u�Εď]����ʂ��Ă̑ΕĎ����v�Ƃ��������{�̍��Ɛ헪�͂����Ɏ����āA�قƂ�NjY��̃��x���ɂ܂��⏬������Ă��܂����Ǝv���܂��B
������A���ꂩ�����ނ͓����p�^�[�����J��Ԃ��Ǝv���܂��B�Εď���������ɁA�A�����J���}���肻���Ȃ��Ƃ�����B�ނ��猩����A�܃|�C���g���������̂ŁA�܃|�C���g�l�������B���ꂪ�O�����A�ƁB�ގ��g�́A����ɂ���āA�A�����J�ƃC�[�u���p�[�g�i�[�Ƃ��đΓ��ȊO���������Ă������ł���Ǝv����ł��B
���Ԃ��������Ə\�������Ȃ��̂ŁA�ł͈�̂��ꂩ���X�͂ǂ�����Ď匠���ƂƂ��āA�匠���Ƃւ̓�����炢�����Ƃ������Ƃ��q�ׂ����Ǝv���܂��B
���Ƃ������̂��A�F����͂��Ԃ��I�ɕ\�ۂ��Ă���Ǝv���܂��B
�r�W�l�X�}���͂����ł��B�����̎��v�Ƃ��A�����Ƃ������Ƃ���l���Ă���l�́A����Ɠ����悤�ɍ��̂��Ƃ��l����B�ł�����A���E�𐅕��I�ɁA���I�Ɂu�n�}�v�Ƃ��ĕ\�ۂ��āA���̒��ł̎��������̎�蕪�͂ǂꂮ�炢���A�p�C�̂ǂꂮ�炢������Ă��邩�B���������悤�Ȍ`�ō��Ђ⍑�͂��i�t�����Ă悤�Ƃ��Ă���B����ǂ��A�{���̍��Ƃ����̂͋�ԓI�ɕ\�ۂ�����̂ł͂Ȃ��A�l�͂����v���Ă��܂��B�n�}�̏�̔����̍L���Ƃ��A���͌��Ƃ������̂���I�ɕ\�ۂ��āA���ꂪ���͂ł���ƍl����̂́A�Ԉ���Ă���Ǝv���B
���Ƃ����̂͂����������̂ł͂Ȃ��āA���ۂɂ͐��������A���Ԃ̒��ł������Ă�����̂ł��B��X�����̍������L���Ă���A���{�Ȃ���{�Ƃ������̍\�������o�[�Ƃ����̂́A������ɐ����Ă���l�Ԃ����ł͂Ȃ��B�����ɂ͎��҂��܂܂�Ă��邵�A���ꂩ�琶�܂�Ă���q���������܂܂�Ă���B���̐l�����ƁA��̑��זE�����̂悤�ȋ����̂��������͌`�Â����Ă���B�����ɁA���Ƃ������̂̂ق�Ƃ��̋��݂�����Ǝv���܂��B
�ߌ��r�コ��́A�J�풼�O�Ƀn�[�o�[�h��w�𑲋Ƃ���킯�ł�����ǂ��A���̂Ƃ��ɃA�����J�Ɏc�邩�A�����D�œ��{�ɋA�邩�Ƃ����I���̂Ƃ��ɁA���{�ɋA��Ƃ����I�������܂��B�����͐��������A�����J�ɂ��āA�p��ŕ����l����悤�ɂȂ��Ă��܂������A���{������ڂ��Ȃ��Ȃ��Ă���B�����������{�̐����Ƃ��ǂ̒��x�̐l�����悭�킩���Ă��邵�A�����A���{�͂��ꂩ��푈��������畉���邾�낤�B�����܂ł킩���Ă�������ǂ��A���{�ɋA��A�������ӂ���B���̂Ƃ��̗��R�Ƃ��Ēߌ��������Ă���̂́A������Ƃ��ɂ͎����́u���Ɂv�ɂ������A�Ƃ������Ƃł����B
�u���Ɂv�ƂƂ��ɐ������ɂ������Ƃ����̂́A����́A��͂肷�����d�������Ƃ��Ǝv����ł��B���̊��o�Ƃ����̂́A�Ȃ��Ȃ������w�̗p��ł͂��܂����邱�Ƃ��ł��Ȃ���ł�����ǂ��A�ȒP�ɑz���̋����̂��A�������z���Ƃ��������Ă��܂��Ă͍���B�Ƃ����̂́A���ۂɁA��X���{�l�́A���ݗɋ��Z����ꉭ�O�疜�l�����łȂ��A���҂������A���ꂩ�琶�܂�Ă���q���������A�������{�l�̃t�������o�[�ł��邩��ł��B�ł�����A�ߋ��̎��҂����ɑ��ẮA�ނ炪�Ƃ������Ɋւ��ẮA��X�͎p���Ȃ�������Ȃ��B�����āA�ł����犮�ς��āA�ł��Ȃ���A�ł��邾���y�����āA������ɑ���o���Ȃ�������Ȃ��B���̎d�����l��ɉۂ���Ă��邾�낤�Ǝv���Ă��܂��B
���̓��{�ł̓O���[�o���Y���ƃi�V���i���Y�����������Ă��܂��B�O���[�o���X�g�͂����Γ����ɖ\�͓I�Ȕr�O��`�҂ł�����B�l�͂���͕ʂɕs�v�c���Ƃ͎v��Ȃ��B����͔ނ炪�܂��ɐ��E����I�ɑ����Ă��邱�Ƃ̌��ʂ��Ǝv����ł��B�O���[�o���Ȑw�n���Q�[���ŁA���������́u��蕪�v�u�V�F�A�v�𑝂₻���Ƃ��Ă���B���̓_�ł̓O���[�o�����{��`�҂Ɣr�O�I�i�V���i���X�g�͂܂��������^�I�Ȏv�l�����Ă���B
�����āA�r�O��`�i�V���i���X�g�Ƃ����̂́A�`�������Ɋւ��đS���S�������܂���B���҂ɑ��ĊS���Ȃ�����ł��B�ނ�ɂƂ��Ď��҂Ƃ����̂́A�����̖T�Ƃ��ĕ֗��ȂƂ��ɌĂяo���āA�g�������邾���̑��݂ł��B�s���̂����Ƃ������s���̂悢�����Ŏg���āA�p�����Ȃ���ΖY��Ă��܂��B�����ɖ𗧂��҂͏d�p���邯��ǁA���������҂�A�����ɓK�����Ȃ����҂����́u���݂��Ȃ����Ɓv�ɂ��ĕ��C�ł��B����͂���炪�u���Ɂv���l���Ă���Ƃ��ɁA�����ɂ͎��҂����ꂩ�琶�܂�Ă���l�������܂܂�Ă��Ȃ�����ł��B
�ł��A�l�������ŏI�I�Ɂu���Ɂv�𗧂Ē����A�ق�Ƃ��Ɂu���Ē����v�Ƃ���܂Œǂ��l�߂��Ă���Ǝv����ł�����ǂ��A���Ē����Ƃ��ɖl�炪���߂鎑���Ƃ����̂́A���ǁA������Ȃ��킯�ł��B
��͎R�͂ł��B���j��ĎR�͂���B���̂��łтĂ��A�o�σV�X�e�����������Ă��A�R�͎͂c��܂��B�����ɑ�������߂邵���Ȃ��B������͎��҂ł��B���҂�������②���ꂽ���̂ł��B�����l�����̑�Œf�₳���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����̐���ɓ`���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����Ӗ��̊��o�ł��B
�R�͂Ƃ����̂͌���ł���A�@���ł���A�����K���ł���A�H�����ł���A�V����J�ł���A���邢�͎R�������̌i�ςł��B��X���g��{���āA��X���g�݁A�����x���Ă���悤�ȁA�l�H�I�Ȃ��̂Ǝ��R���������ݍ����Ă���ꂽ�A��̔��ɕ��G�Ȕ|�{��̂悤�Ȃ��́A�l�͂�����R�͂ƌĂт����Ǝv���Ă��܂��B�R�͂Ƃ͉����Ƃ������Ƃ��A���ꂩ���A�l�͂�����ƌ��t�ɂ��Ă��������Ǝv���Ă��܂��B
������͎��҂����ł��B���҂������A�����̐�����A���͂܂����݂��Ȃ��҂��A��X�̂��̍��̐��K�̃t�������o�[�ł����āA�ނ�̌����A�ނ�̋`���ɑ��Ă��z�����Ȃ�������Ȃ��B
�l�͍��C��������Ă���킯�ł�����ǂ��A�o���I�ɂ킩�邱�Ƃ̈�Ƃ����̂́A�Ⴆ�Α̂����ƁA�����̑̂̋ؓ��A���i�Ƃ��A�߂Ƃ��A�����������̂𑀍삵�悤�Ǝv���āA��̓I�ɁA���A���݂�����̂����������Ă����Ă��̂͐���Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�������A�Ⴆ���A��̓��ɓ��������Ă���B�����ɕ��������āA�n�������āA���悪�����ɂ���B��Ɏ����Ă��Ȃ����̂��C���[�W���đ̂��g���ƁA�S�g�������B
����͒����m�Â��Ă悭�킩�������ƂȂ�ł�����ǂ��A���ۂɂ́A��X�͍��A���݂�����́A�����ɋ�̓I�ɕ��Ƃ��Ă�����̂�ςݏグ�Ă����āA��̑g�D��W�c�������Ă���̂ł͂Ȃ��āA�ނ���u�����ɂȂ����́v���肪����ɂ��āA�g�D��g�́A�����̂Ƃ������̂𐮂��Ă���B����́A�l�͎����Ƃ��Ă킩���ł��B
���A���{�l�ɋ��߂��Ă�����̂Ƃ����̂́A���{�l�����̐S�g�𐮂���Ƃ��̂��ǂ���ƂȂ�悤�ȁu���݂��Ȃ����́v���Ǝv���܂��B���݂��Ȃ��̂�����ǁA���肠��Ǝv�������ׂ邱�Ƃ��ł�����́A�������ɂ����Ɗ������Ƃ��ɁA�����͂�����������́A�����̑̂��S�������Ă��āA����ׂ��Ƃ��ɁA����ׂ��Ƃ���ɂ���Ƃ���������^���Ă������́B�����Ƃ����͎̂�����������n���ł͂Ȃ��āA��������邱�Ƃɂ���đ̂������āA������u�ˑ�v�Ƃ��ċ���Ȏ��R�̗͂��̂ɗ��ꍞ��ł���A����������̑��u�Ȃ킯�ł��B����́A��̓��ɂ����Ă��������A�Ȃ��Ă������B�ނ���A�Ȃ��ق��������̂����m��Ȃ��B
���A���{���匠���ƂƂ��čĐ����邽�߂ɁA�l��ɕK�v�Ȃ��̂�����ɋ߂��悤�ȋC�����܂��B���݂��Ȃ����́A���݂��Ȃ��ɂ�������炸�A���{�Ƃ������𐮂��āA���������ׂ��Ƃ��ɁA����ׂ��Ƃ���ɗ������A�Ȃ��ׂ����Ƃ������Ă����悤�Ȃ��́B���̂悤�Ȏw��͂̂���u���݂��Ȃ����́v���肪����ɂ��č�������čs���B
���{�����@�͂��̂悤�Ȃ��̂̈���Ǝv���܂��B���z��`�I�Ȍ��@�ł�����A���̌��@�����߂Ă���u�ꐧ�Ɨ�]�A�����ƕ���n�ォ��i���ɏ�������v���Ƃ͂��Ԃ��i���������Ȃ��B�n��ł͎�������͂����Ȃ��B�ł��A���̂悤�ȗ��z���f����Ƃ������Ƃ͍��̂������𐮂����Ŕ��ɗL���Ȃ킯�ł��B���̂��߂ɂ��̍�������̂��A�����̍��Ƃ͉����������邽�߂ɑ��݂���̂��Ƃ������Ƃ�m�邽�߂ɂ́A��X���������Ă���A���ɂ��ǂ�����Ƃ̂Ȃ����������_�Ȃ���̂���������Ƃ��܂Ȃ�������Ȃ��B����Ȃ��ł͂ǂ̂悤�ȑg�D�������䂫�܂���B
���ꂩ��ǂ�����ē��{�Ƃ������𗧂Ē����Ă����̂��l����Ƃ��ɂ́A�˂Ɏ��҂����ƁA�������܂�Ă�����҂����ƁA�����Ă��鎩����������̓��E�Ƃ��Č���Ă���A���������l���������邵���Ȃ��̂��ȂƎv���Ă���܂��B
���ꂩ����{�͈�̂ǂ��Ȃ��Ă����̂��B���́A�l�͂��܂�ߊς��Ă��Ȃ���ł��B�����܂łЂǂ��������ƁA�����牽�ł������͕ۂ��Ȃ��Ǝv����ł��B���ɁA���⍑�ێЉ�̏�������A����������ƍ����I�Ȏv�l�����鐭���Ƃɓ������Ă��炢�����Ƃ��������v��������Ǝv����ł��B�����łȂ��ƊO�����Q�[���ɂȂ�Ȃ�����B
���݂̓��{�̈��{�����Ƃ����̂́A�A�����J�Ƃ��A�����Ƃ��A�؍��Ƃ��A�k���N�Ƃ��A���V�A�Ƃ��A�ߗׂ̍��A�ǂ��Ƃ����O�������ł��Ȃ���Ԃł��ˁB�قƂ�ǁu���Ȃ��Ă����v�ƌ����Ă���킯�ł��B���{�����̂ǂ��Ƃ������I�Ȏ�]��k���ł��Ȃ��̂́A�ނ̍��Ɛ헪�ɑ��āA�ق��̍��X�Ɉ٘_������A�����Ȃ��Ƃ������Ƃł͂Ȃ��Ǝv���܂��B���{�̍��Ɛ헪���킩��Ȃ�����ł���ˁB����ł́A�����悤���Ȃ��B
���{���I�����Ă��鐭��́A���邢�͒P�Ȃ鐭���I�����̂��߂̂��̂Ȃ̂��Ǝv������A�O���͕|���āA����Ȑl�Ƃ͊O�����͂ł��Ȃ��ł��傤�B�l�I�Ȑ����I�����̂��߂ɍ��������E����悤�Ȑl�ԂƂ͒N�����Č��������Ȃ��B���܂�ɕs����ł�����B���ƍ��Ƃ̖́A�����Ŗ������Ƃ��ܔN�A�\�N��������ƌp������A�����̈ӎv�܂��Ă��Ȃ��ƈӖ����Ȃ��B�ł��A���{����̊O���͂ǂ����Ă������̑��ӂ��\���Ă�����̂Ƃ͎v���Ȃ��B���{�������u��\���Ă�����Ă��Ȃ��v�Ǝv���Ă���Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�����̎�]���u���̐l�̌��t�͍��̖Ƃ��ďd�邱�Ƃ��ł���̂��v�ǂ����^��Ɏv���Ă��邩��ł��B�ł�����A���ꂩ���A���{�����ł������A�ΕāA�Β��A�ΊA���V�A�̂ǂ̊O���W���͂��������i�W�͂Ȃ��Ǝv���܂��B�ǂ̍����u���̎v�Ƃ��Ă����������̂̂킩�����l�Ԃ��o�Ă��邱�Ƃ�҂��Ă��āA����܂ł͖�����悤�Ȗ͌��킳�Ȃ�����ł���Ǝv���܂��B
���{�����Ɋւ��ẮA�l�͂���قǒ����͕ۂ��Ȃ��Ǝv���܂��B���Ɏ����}�̒��ł��A����_���Ă���l�����������o���Ă���B�����A��قǘb�����悤�ɁA�Εď]����ʂ��Ď��ȗ��v�𑝂��Ƃ����u���ك}�C���h�v���������l�������A���݂̓��{�̃G�X�^�u���b�V�������g���\�z���Ă���Ƃ����d�g�ݎ��̂ɂ͕ω����Ȃ��ȏ�A���{���ޏꂵ�Ă��A���ɏo�Ă��鐭���Ƃ���͂�ʎ�́u���ِ����Ɓv�ł��邱�Ƃɕς��͂Ȃ��B�Ŕ͕ς���Ă��A�{���͕ς��Ȃ��Ǝv���܂��B
�ǂ�������炱�̂悤�Ȑ����̐���ᔻ�ł���̂��B�l���w�p�Ƃ������̂��ŏI�I�ɐM���Ă���̂͂����Ȃ�ł��B�א��҂Ɍ������āA���Ȃ����͂����������W�b�N�ɏ]���Ă��̂悤�Ȑ������f�����āA���Ȃ����͂����������@�ł��̐�����̗p���A�����������v���m�ۂ��悤�Ƃ��Ă���A���������Ƃ��͂����荐����Ƃ������Ƃł��B����͂Ƃ������A�����Ƃ��āA�ނ琭���Ƃ������ǂ��������J�j�Y���œ����Ă�����̂Ȃ̂����͂�����ƊJ������B�{�l�ɂ��A�����S�̂ɂ��J������B�ʂɔނ炪�ۗ����Ď��ł���Ƃ��A��݂ł���Ƃ������K�v�͂Ȃ��B�ނ�̒��ɑ����Ă����ϓI�Ȏ����ѐ��A�������������ɂ��Ă䂭�B���̍�Ƃ��ł�������]���������Ă��邾�낤�Ɩl�͎v���܂��B
�@
�l�́A�m�b�ƌ��t�������Ă���͂Ƃ����̂͂ƂĂ��傫���Ǝv����ł��B�ʂƌ������āA�u���܂��͊Ԉ���Ă���v�Ƃ��A�u���܂��͌������v�Ƃ������Ă����߂Ȃ�ł��B�����ł͂Ȃ��āA�u���Ȃ��͂����l���Ă���ł��傤�B������A���A��������ł��傤�B���Ȃ��̓��I���W�b�N�͂���������A���Ȃ������邱�Ƃ����ɂ͗\���ł���v�ƁB���b�ɏo�Ă���u�T�g���v�ł͂Ȃ��ł�����ǁA���l�ɂ��̂�v�l�̓��I�\�����������Ă���ƁA�l�Ԃ̓t���[�Y���Ă��܂��āA��낤�Ǝv���Ă������Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�l�̖\�����~�߂悤�Ǝv������A���̐l�����ɂ�肻���Ȃ��Ƃ������Ό������ĂāA���̂Ƃ��ɂǂ�������`�����𗧂Ă邩�A�ǂ���������������邩�A�S�����肵�Č������ĂĂ��܂������B����������ƁA����ꂽ���͂��������ȋC���ɂȂ�Ǝv����ł��B�������Ă�ꂽ��s����������A����͎~�߂āA���Ⴀ�Ⴄ���Ƃ���낤�Ƃ������ƂɂȂ����������B���������������ł���A�����̓k�ł������ߒ��Ɋ֗^���邱�Ƃ��ł���B�l�͂��������ӂ��ɍl���Ă��܂��B
�����f���N���V�[�̉�ɂ͑����̒m�����W�����Ă���킯�ł����A�l�͂��������l�b�g���[�N�𐭎��I�ȉ^���Ƃ��ēW�J����Ƃ������Ƃɂ͎��͂��܂苻�����Ȃ���ł��B���̐����I�L�����ɑ��Ă��A���Ɖ��^�I�Ȃ�ł��B�^�ɐ����I�Ȃ��͎̂��͒m���̓������Ǝv���Ă��邩��ł��B
���A�����N���Ă���̂��A���A�����ɓ��{�ō����̑ǂ��Ƃ��Ă���l�����������l���Ă���̂��A�ǂ������~�]�������Ă���̂��A�ǂ��������ӎ��I�ȏՓ��ɋ쓮����Ă���̂��A����𔒓��̂��Ƃɂ��炵�Ă����Ƃ�����Ƃ��A���ۂɂ̓f���������菐�����W�߂��肷������A���ɂ���Ă͉��S�{����{�����ʓI�Ȑ����I�ȗ͂ɂȂ邾�낤�Ɩl�͐M���Ă���܂��B
���ꂩ������������}�݂Șb�����������Ō�葱���鏊���ł������܂��B���Ƃ����̌��t�����{����ɓ͂��āA�ނ��������s�����ȋC���ɂȂ��Ă���邱�Ƃ��A�����ĉ��͂���Ȃ��Ƃ��l���Ă���̂��ƒm���āA������Ɯ��R�Ƃ���Ƃ����������邱�Ƃ����҂��āA���_�����𑱂��Ă܂��肽���Ǝv���Ă���܂��B�F������̂��������F���Ă���܂��B�������A�ǂ������肪�Ƃ��������܂����B

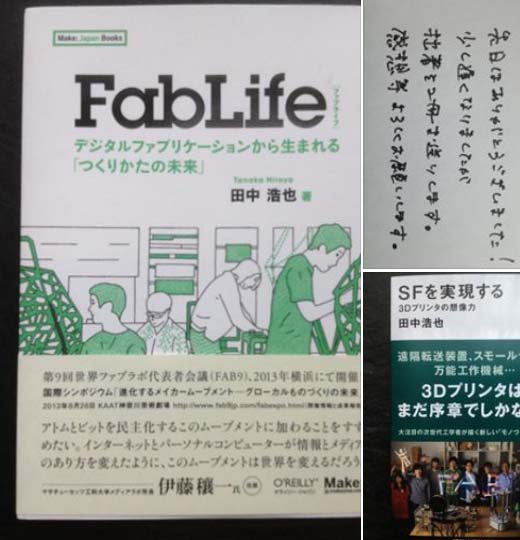
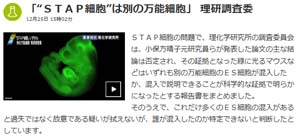

 ����B��C�J���Ă��ďݖ��ȂǂŐZ���u���@�̂��@�l�Q�����ݓ��ꂩ������������������̏o���オ��B
����B��C�J���Ă��ďݖ��ȂǂŐZ���u���@�̂��@�l�Q�����ݓ��ꂩ������������������̏o���オ��B













